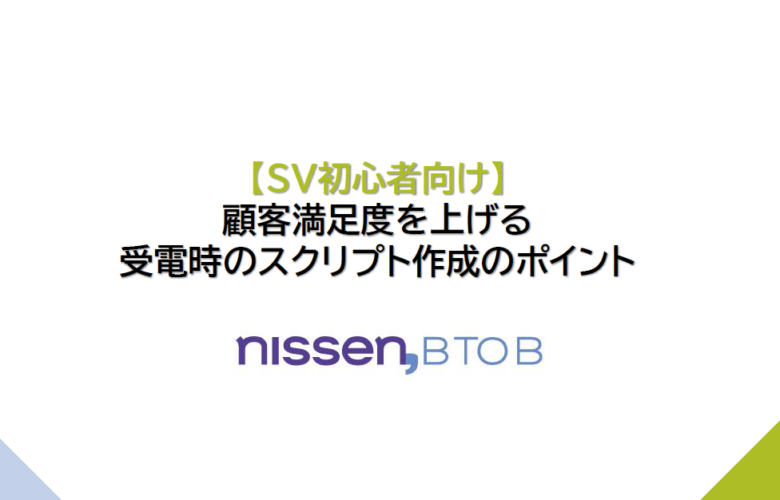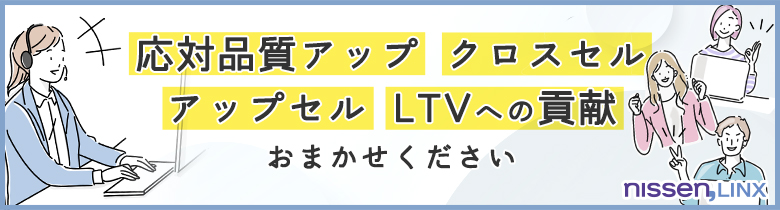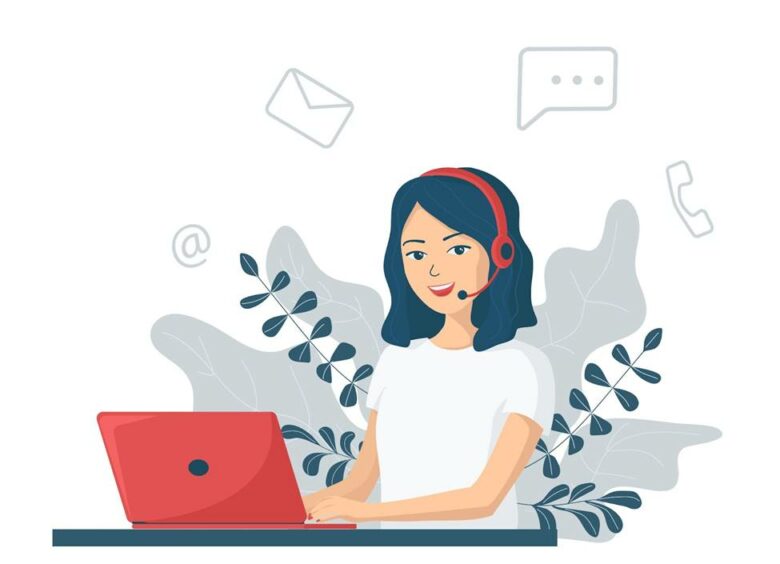コールセンター代行とは、企業が顧客対応業務を外部の専門会社へ委託するサービスのことです。電話対応や受注処理、テクニカルサポートなど、幅広い業務を専門家に任せることで、コスト削減やサービス品質向上を図る企業が増えています。
本記事では、コールセンター代行の概要からメリット・デメリット、導入までの手順、そして費用相場や会社の選び方まで幅広く解説します。自社の状況や目的に合った導入判断の参考にしてください。
さらに、コールセンター代行の具体的な費用体系や成功事例にも触れながら、導入前に押さえておきたいポイントを網羅的に紹介します。初心者の方でも理解しやすいように、専門用語はできるだけ平易にまとめました。
委託先の応答率や対応品質が悪い、、コールセンターのコストを削減したい、、業務の生産性をあげたいといった課題がありましたら、是非DLくださいませ
コールセンター代行とは何か
まずはコールセンター代行の定義や特徴を整理し、コンタクトセンターとの違いについて概観します。
コールセンター代行は、企業の顧客対応を専門会社が一手に引き受けるサービスです。多くの場合、電話による問い合わせ受付や商品注文対応などに加えて、メールやチャットを活用する場面もあります。顧客対応業務を外任することで、自社の人員をコア業務に集中させながら、高品質なサポートを提供できるようになる点が特徴です。
特に近年は、企業活動のグローバル化やECサイトの普及に伴い、顧客からの問い合わせや注文が24時間体制で発生するケースが増えています。それに対応する新たな負担を、専門のオペレーターを抱える代行サービスへ委託することで、迅速かつ効率的な顧客対応を実現する流れが強まっています。
コールセンター代行の定義と特徴
コールセンター代行は、企業の電話対応や受注処理など、多岐にわたる顧客接点業務を外部企業が代行する形態を指します。インバウンド業務(受信対応)やアウトバウンド業務(発信対応)などの幅広い電話関連タスクを行える点が大きな特徴です。専任のオペレーターが常に待機しているため、急なコール数の増加にも柔軟に対応できます。
また、代行会社が持つ研修プログラムや品質管理システムを活用することで、短期間で高品質なコール対応を始められる点も魅力です。人材育成やシステム投資にかかるコストを外部に任せることで、クライアント企業は自社のリソースをより戦略的な領域に振り向けやすくなります。
コンタクトセンターとの違い
コールセンターとコンタクトセンターはしばしば混同されがちですが、コールセンターが電話対応に特化しているのに対し、コンタクトセンターは電話のほかにメールやチャット、SNSなど、複数のチャネルでの顧客対応を含む点が異なります。最近では、どちらの機能も担う企業やサービスが増加し、顧客との接点を幅広くサポートする動きが主流となっています。
ただし、自社の顧客が主に電話対応を求めている場合はあえてコールセンター機能のみを利用するケースもあります。一方で、オンラインショップや海外との取引が多い企業などでは、複合チャネルを扱えるコンタクトセンターの方が向いている場合もあります。自社のビジネスモデルや顧客属性を鑑みながら、最適なサービス形態を選ぶことが重要です。
ニッセンLINXのコールセンター業務支援について、詳しくはこちら
コールセンター代行で依頼できる主な業務
コールセンター代行では、インバウンド(受信)業務とアウトバウンド(発信)業務の2種類を中心にサービスが展開されます。
コールセンター代行会社では、企業が行っていた電話業務を幅広くカバーできる体制を整えています。たとえば、商品の注文受付や問い合わせ対応といったインバウンド業務にとどまらず、顧客に対して新商品の提案やアンケート調査を行うアウトバウンド業務にまで対応している会社もあります。
複数の業務を同時に依頼できるため、プロモーション施策の一貫として発信業務を強化しながら、既存顧客の問合せ対応も統合的に依頼するといった柔軟な使い方が可能です。自社では人件費やスタッフ教育のコストがかさむ業務も、専門オペレーターを活用することで効率化できます。
インバウンド(受信)業務
インバウンド業務とは、電話やメール、チャットなどを通じて顧客から寄せられる問い合わせや注文、クレーム対応を担うサービスを指します。商品やサービスに関する疑問、サポート依頼、トラブル対応など、多様な要望に即時に応えることで満足度を高めることが重要です。
コールセンター代行会社では、顧客対応のプロが事前に研修やマニュアルを習得しているため、企業のブランドイメージを損なうことなく、丁寧で的確な対応をスピーディーに行えます。受注業務の場合は決済手続きや在庫確認まで代行し、企業のバックオフィス作業を大幅に削減する事例も珍しくありません。
コールセンターのインバウンド業務とは?仕事内容や効率的に運営する方法まで解説はこちら
インバウンドにおける必要スキル、スクリプトの基本構成等、顧客満足度を上げる受電対応時のスクリプト作成のポイントをまとめています
アウトバウンド(発信)業務
アウトバウンド業務は企業側から顧客へ電話をかける業務を意味し、主に営業電話やキャンペーン案内、アンケート調査、リード獲得活動などを行います。商品やサービスを広めたり、顧客満足度調査を実施したりと、マーケティング活動の一環として活用されることが多いです。
代行会社は、ターゲットリストの作成からアプローチ方法の策定、応対結果の分析に至るまで、専門ノウハウをもとに総合サポートを行います。自社で行うよりも効率的に見込み客や顧客からのフィードバックが集まり、成約率の向上や顧客満足度向上施策に役立つ点が魅力です。
コールセンターのアウトバウンド業務とは?成功に導く7つのポイントはこちら
アウトバウンドの作成方法は、下記にわかりやすくまとめた資料がありますので、ぜひご活用ください。
コールセンター管理者必見!成果が出るアウトバウンドのスクリプト作成のノウハウやポイントを紹介。
アウトバウンドのコールセンター担当の方向けには、下記の資料がおすすめです。
コールセンター担当者必見!成果改善に役立つアウトバウンドコール(営業電話)のポイントを紹介します。
コールセンター代行のメリット
コールセンター代行を利用することで得られる主なメリットについて解説します。
コールセンター代行を導入すると、顧客とのコミュニケーション円滑化や人件費の削減など、さまざまな恩恵を受けることが可能になります。自社内でコールセンターを運営する場合に比べ、システム投資やオペレーターの確保などの負担が軽減されるケースが多く、必要な時に必要な対応力を確保できる点が魅力です。
さらに、熟練したコールスタッフや専門知識をもったオペレーターが応対を担当するため、顧客の多様なニーズに応じて的確かつ迅速なソリューションを提供できます。その結果、企業のブランドイメージ向上や顧客満足度の向上にも直結する効果を期待できます。
コスト削減と業務負担の軽減
自社でコールセンター機能を内製すると、オペレーターの募集や採用、研修、システム導入にかかる費用が大きくなってしまいます。一方、代行サービスを利用することで初期投資が抑えられ、オペレーターの教育や勤怠管理などの負担も減らせます。必要なときだけサービスを拡張・収縮できるのも魅力です。
特に繁忙期やキャンペーン時など、問い合わせの量が不規則に増減する企業にとっては、柔軟に体制を整えられることが大きな利点です。業務負担が軽減され、人件費の変動リスクを最小限にした上で顧客対応を維持することが可能となります。
専門知識・ノウハウの活用
コールセンター代行会社は長年にわたって蓄積されたノウハウを活用し、業務効率化や顧客満足度向上のための最適解を提供します。オペレーターの教育プログラムが充実しているため、商品やサービスの特性を理解したうえで質の高い対応を実施できます。
さらに、最新のCTI(Computer Telephony Integration)システムや顧客管理ツールを駆使して、顧客情報や対応履歴を一元管理しやすい環境を整えてくれるケースもあります。これにより、一般的なカスタマーサポートだけでなく、テクニカルサポートや特殊な問い合わせにも迅速に対処できる点が強みです。
顧客満足度・CXの向上
顧客が抱える不満や疑問を迅速に解消し、適切な解決策を提示できれば、その企業やサービスに対する信頼度は高まります。コールセンター代行では、敬語や電話マナーに慣れたオペレーターが応対するため、スムーズで好印象なコミュニケーションが行われる点が特徴です。
顧客体験(CX)の質が高い企業ほどリピート率が上がる傾向にあるため、代行活用によって顧客対応のクオリティ向上を図ることは、長期的な顧客ロイヤルティの獲得にもつながります。また、クレームやトラブル時の迅速な対応は、企業イメージの保全・改善に欠かせません。
BCP対策と安定稼働
自然災害やパンデミックなど、想定外の事象が発生した場合でも、コールセンター代行会社が複数拠点で稼働していれば顧客対応が途切れるリスクを低減できます。緊急時にも安定したサービスを提供できる体制は、企業の信頼維持に直結します。
また、常時稼働や24時間受付などの柔軟な運用にも対応できるため、国内外の顧客を相手にする企業や時間外問い合わせが多いサービスなどにとって、不可欠な仕組みとなっています。こうしたリスク分散は、企業の継続的な成長を支える重要な一要素です。
委託先の応答率や対応品質が悪い、、コールセンターのコストを削減したい、、業務の生産性をあげたいといった課題がありましたら、是非DLくださいませ
コールセンター代行のデメリット・注意点
利用にあたってはリスクや課題も理解しておく必要があります。
コールセンター代行を活用することで得られる恩恵は大きい一方、外部委託ならではの懸念点も見逃せません。例えば、情報漏洩やセキュリティ管理が不十分な場合、企業ブランドへの悪影響につながるリスクがあります。
また、顧客対応に関するノウハウが社内に蓄積されにくいという面もあり、将来的に企業自ら蓄積した知見を活かせない可能性が生じることにも留意が必要です。こうしたデメリットを理解した上で、適切な対策や運用体制を整えることが導入成功の鍵となります。
情報漏洩リスクとセキュリティ管理
コールセンター代行では、多くの場合、顧客の個人情報や注文履歴などが取り扱われます。外部委託先が十分なセキュリティ対策を行っていない場合、情報漏洩リスクが高まる可能性があります。そのため、業務委託契約を結ぶ前に、セキュリティ管理体制や取得している認証(ISMSやプライバシーマークなど)を確認することが必須です。
加えて、オペレーターが扱う情報の範囲を必要最小限に限定し、アクセス権限の設定や定期的な監査の実施など、具体的な対策が行われているかをチェックすることが望ましいでしょう。問題が発生した際の対応体制も含め、事前にルールを明確化することでトラブルを回避しやすくなります。
ノウハウが社内に蓄積しにくい
コールセンター運営を自社で行う場合、顧客対応を重ねるうちにどういったトラブルが多いか、どんな問い合わせが増えているかなど、多様な知見が自然と社内に集積されます。しかし、代行に任せていると、その知見が外部にしか蓄積されないという問題が生じやすくなります。
この課題を解消するには、定期的にレポートを受け取り、問い合わせ内容の傾向分析や顧客からの生の声を社内へフィードバックする仕組みを整備することが大切です。社内各部門がその情報を活用してサービス改善や新規商品開発を進めることで、外部委託のメリットを最大化できます。
顧客ニーズの反映が遅れやすい
コールセンターを外注していると、現場感覚に基づく柔軟な対応が遅れるリスクがあります。特に、新しいキャンペーンを迅速に案内したい、特別な要望に応じてアプローチを変えたいといった場合、委託先との連絡や運用フローの見直しが必要になるため、どうしても即応性が低下する可能性があります。
こうした問題を回避するためには、代行先とのコミュニケーション・打ち合わせを密に行い、ガイドラインの更新やオペレーターへの周知をこまめに実施することが不可欠です。日頃から情報共有を大切にし、顧客ニーズを早期に代行会社へ伝える仕組みを築いておきましょう。
クレーム対応の基本と正しい方法、テクニックについて徹底解説!こちら
コールセンター代行の費用体系と相場
コールセンター代行の料金形態は主に月額固定型と従量課金型にわかれます。導入前にしっかり比較検討しましょう。
費用体系を理解するうえでは、どのようなプランが自社の業務形態や予算に合致するかを見極めることが重要です。月間のコール数が一定しているのか、それとも季節によって大きく変動するのかなど、自社特有の状況を把握する必要があります。
また、初期導入費用やオプションの有無によっても総コストは変わってくるため、見積もり時に詳細を確認することが欠かせません。いずれのプランを選ぶにせよ、目的とする顧客対応の範囲や必要なサービスレベルを明確にしておくことが大切です。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援しているクライアントへ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
月額固定型の料金プラン
月額固定型の料金プランでは、あらかじめ設定した範囲の業務を毎月一定料金でまかなう形となります。電話対応件数やオペレーター稼働時間に多少の増減があっても、費用がフラットになるため予算が立てやすい特徴があります。
業務量が一定しており、毎月の問い合わせ件数が読める企業には適したプランです。一方で、実際の問い合わせ数が予想よりも少なくても固定費は支払い続けるため、余分なコストが発生するリスクがある点には注意が必要です。
従量課金型の料金プラン
従量課金型では、実際の通話数や応対時間、もしくは成果に応じて費用が変動する仕組みが一般的です。ある程度コール数が予測しづらい場合や、キャンペーンなど一時的にコールが急増する可能性がある場合に選ばれます。
繁忙期のみアウトバウンド業務を強化したい、あるいはインバウンドでの問い合わせがある一定の期間だけ集中するといったビジネスモデルを持つ企業に最適です。ただし、コール数の増加分がそのままコストに跳ね返るため、一時的な支出が高額化する可能性もあります。
初期導入費用やオプション費用の確認
コールセンター代行を始める際には、システム導入費やオペレーター教育費として、初期導入費用が発生する場合があります。これらの費用は契約プランや代行会社によって異なるため、導入初期の予算計画を立てる際に必ず見積もりで確認しておくことが大切です。
また、夜間対応や多言語対応など、特別なオプションサービスを利用する場合には別途費用がかかる可能性があります。自社の必須要件を明確にして、どのオプションが必要なのかを洗い出すことで、最適な費用対効果を得られる代行プランを見極めることができます。
「通販のニッセンLINX」の会員DB、ノウハウ、インフラを活かし、企業様に対して、プロモーションやテレマーケティング、フルフィルメント(物流支援・コールセンター)、同梱同送などのビジネスソリューションをご提供します。
インバウンド業務の費用相場
インバウンド業務を外注する場合の大まかな料金目安について説明します。
インバウンド業務は顧客からの問い合わせや注文対応など、企業の顔となる大切な役割を担います。コールの内容や対応時間が顧客満足に直結するため、品質管理や応対速度が費用にも大きく影響します。
一般的に1コールあたりや1分あたりの単価が設定されていることが多く、月間の対応件数や平均通話時間に基づいて合計費用が算出されます。費用の見積もりを行う際は、コール種類の内訳や時間帯別のコール数など、詳細な要件を提示しておくことがおすすめです。
問い合わせ受付・受注対応の料金目安
商品やサービスに関する問い合わせ受付や、注文対応を含むコールセンター業務では、1コールあたり200円~500円程度の従量料金を設定している代行会社が多い傾向にあります。月額固定のプランでは数十万円からスタートすることもあり、業務内容やコール数によって変動幅が大きい点が特徴です。
クライアント企業が求める応対品質レベルや特別なスクリプト対応が必要な場合は、別途研修料金やオプション費用が加算されることもあります。事前に応対範囲やシナリオを詰めたうえで詳しい見積もりを行うことで、適切な費用設定を把握しやすくなります。
24時間対応の費用設定
24時間365日の電話対応を希望する場合、通常の営業時間外に稼働するオペレーターの人件費やシフト管理コストが必要となるため、追加費用がかかります。特に、深夜や早朝対応には特別な手当が必要となるケースも少なくありません。
その一方で、顧客にとっては常時対応が可能という安心感が得られ、競合優位性を高められる点がメリットです。24時間対応プランの導入を検討する際には、費用対効果をしっかりと見極め、どの程度のコール数や潜在顧客ニーズがあるのかを把握しておく必要があります。
委託先の応答率や対応品質が悪い、、コールセンターのコストを削減したい、、業務の生産性をあげたいといった課題がありましたら、是非DLくださいませ
アウトバウンド業務の費用相場
アウトバウンド業務のコストについて、最適なプランを選択するポイントを解説します。
アウトバウンド業務では、営業やキャンペーン、アンケート調査など、多岐にわたる発信業務を一括して委託できます。コール数や通話時間、または成果に応じて費用が変動する仕組みが多いです。
厳密なトークスクリプトが必要な場合や成約率が重視される場合には、オペレーターのトレーニングに追加費用がかかるケースもあります。事前に具体的な目的を定め、求める成果指標(KPI)をはっきりさせることがポイントです。
営業電話・アンケート調査の料金目安
営業電話や市場調査などのアウトバウンド業務は、リスト数や想定の通話時間に応じて費用が組まれるのが一般的です。1件あたりの架電単価を数十円から数百円程度とする場合や、通話時間の合計によって課金されるプランなど、さまざまな方式があります。
成約件数やアンケート回収率を高めるためには、質の高いリストと的確なアプローチが重要です。代行会社と相談しながら、最適な方法でターゲットにアプローチし、多角的に情報を収集する仕組みを整えると、より費用対効果の高い施策が実現しやすくなります。
成果報酬型プランの導入事例
成果報酬型プランでは、契約数や成約率、もしくは商談獲得件数など、目標とする成果指標に応じて費用が発生する仕組みが採用されます。初期コストを抑えたい企業にとっては、費用対効果を測りやすいメリットがあります。
ただし、成果報酬型ではオペレーターのモチベーション管理や正確な成果測定が欠かせず、業務フローが複雑化する場合もあります。成果の算出基準や評価方法を事前に取り決めておくことで、双方にとって透明性の高い運用を行うことが可能です。
「通販のニッセンLINX」の会員DB、ノウハウ、インフラを活かし、企業様に対して、プロモーションやテレマーケティング、フルフィルメント(物流支援・コールセンター)、同梱同送などのビジネスソリューションをご提供します。
コールセンター代行会社の種類と特徴
コールセンター代行サービスは得意分野ごとにさまざまな会社が存在します。それぞれの特徴を理解しましょう。
コールセンター代行会社は、それぞれに強みや得意分野があります。大規模サービスに適した総合力を持つ会社から、特定の業種や言語対応に特化した会社まで、多岐にわたる選択肢があります。
自社の目的や依頼範囲に合った会社を選定するには、まず自社が必要としている業務内容、規模、地域、言語などの条件を整理することが重要です。さらに実績や導入事例をチェックし、サービスの質やサポート体制を把握することも大切です。
大規模案件に強い総合型サービス
大手コールセンター代行会社は、数百席から数千席のオペレーション体制を備えており、コール数が膨大な案件にも対応可能です。大手企業や官公庁などの大規模プロジェクトの実績が豊富で、運用マニュアルや研修システムも充実しているケースが多く見られます。
音声認識システムやAIチャットボットと連携し、マルチチャネルでの顧客対応を統合的にサポートするなど、最新技術を積極的に導入する点も魅力です。ただし、そのぶんコストは高めになる傾向があるため、予算との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。
多言語対応・海外事業に強いサービス
海外展開を行っている企業や、インバウンド観光関連で多言語サポートが必要な企業には、英語や中国語、韓国語など複数言語での対応を得意とするサービスがおすすめです。ネイティブスタッフを確保し、文化や商習慣を理解した応対が行われる場合もあります。
多言語サービスは単に言葉を訳すだけでなく、文化的ニュアンスに合ったコミュニケーションを提供することが重要です。電話対応だけでなくメールやチャット、SNSなど多様なチャネルをサポートしている会社を選ぶことで、海外顧客への利便性が向上します。
通販(EC)業界など特定分野に強いサービス
通販(EC)業界に特化しているコールセンター代行会社では、受注処理や返品・交換対応、配送状況の問い合わせなど、EC特有の問い合わせにもスムーズに対応できるノウハウが豊富です。決済システムとの連携や、在庫管理システムとの情報共有など、EC事業者が求める機能に長けています。
また、キャンペーン時の大量注文対応や物流が混雑する時期に備えた体制など、繁忙期対策が強みとなることもあります。業界特化のサービスを選ぶことで、よりシームレスな運用を期待することができるでしょう。
幅広いBPO業務に対応できるサービス
電話対応だけにとどまらず、バックオフィス業務や事務処理、データ入力なども含めて一括委託できるBPO(Business Process Outsourcing)を提供する会社も多く存在します。企業の管理部門や経理業務までカバー可能な範囲が広いケースがあります。
一元的に依頼できれば、企業側のマネジメント負担が大幅に軽減され、業務フローを統合的に最適化できる利点があります。顧客対応と同時に事務処理が発生するようなビジネスモデルの場合、こうした包括的なBPOサービスの利用が有効となるでしょう。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援しているクライアントへ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
コールセンター代行会社を選ぶ際のポイント
自社に合ったコールセンター代行会社を選ぶためのチェックポイントをまとめます。
コールセンター代行会社を検討する際には、依頼範囲、コスト、運用体制、セキュリティなど多方面にわたる要素を総合的に評価する必要があります。特に、自社の商品やサービスに見合った専門知識を持つ担当がどれだけ配置されるかは、顧客満足度を左右する大きな要因です。
また、契約後にどの程度コミュニケーションを密に行えるか、定期レポートやミーティングの頻度なども安定稼働に欠かせません。コスト面だけでなく、運用品質や柔軟性にも着目して最適なパートナーを見つけましょう。
自社の目的・依頼範囲に合致するか
まずは自社が何を外注したいのかを明確にし、それをカバーできる代行会社をピックアップすることがスタートです。インバウンド業務なのか、アウトバウンド業務なのか、あるいは多言語対応が必須なのかなど、優先度の高い要件を整理しましょう。
そのうえで、具体的なワークフローや求めるサービスレベルを提示し、対応可能かどうかを確認します。ここで齟齬が生じると、導入後のトラブルや追加コスト発生の原因となるため、事前のすり合わせを徹底することが大切です。
費用と予算に見合うサービスか
コールセンター代行の費用は、月額固定・従量課金・成果報酬など様々な方式があります。自社の予算や問い合わせ数の見込み、成果目標を踏まえて、どのプランが最適かを検討する必要があります。
特にスタートアップや中小企業の場合、固定費を抑えて導入したいというニーズが強いため、従量課金型や成果報酬型を選ぶことも一案です。ただし、成果が出るまでに時間がかかる業種や、一定数の問い合わせが常に発生する場合は固定型の方が安くなるケースもあるため、一概にどちらが得とは言えません。
柔軟な運用体制・品質管理体制を持つか
季節性やキャンペーンなどで問い合わせ数が急増する場合、柔軟にオペレーター数を増減できる体制があるかどうかは重要な選定基準です。トラブル時や繁忙期の対応力を事前に確認することで、導入後のスムーズな運用が期待できます。
また、オペレーターの質をどのように維持・向上させているか、研修制度や品質管理のプロセスなども確認しておくと安心です。品質向上の提案を積極的に行ってくれるかどうかも、優良企業を見分けるポイントといえます。
情報セキュリティ・個人情報保護の仕組み
個人情報や顧客データを取り扱う以上、セキュリティの確立は欠かせません。情報漏洩や不正利用が発生すれば、企業にとって大きな信用リスクとなります。代行会社がどのようなセキュリティポリシーを持っているか、ISMS(ISO27001)やプライバシーマーク取得の有無をチェックしましょう。
システム面だけでなく、オペレーターへのセキュリティ教育や監視体制の徹底など、人的リスクへの対策も重要です。セキュリティの観点で妥協をしないことが、自社ブランドを守るうえで不可欠となります。
実績・ノウハウの豊富さ
コールセンター代行を多くの企業が利用している会社は、業界ごとの特性や顧客対応のポイントを熟知している場合が多いです。長年の実績がある企業ほど、トラブルシューティングやスケールアップへの対応力に優れています。
導入事例や成功事例をヒアリングすることで、具体的な成果や課題への対処方法も把握しやすくなります。実績豊富な代行会社は、業務効率化やサービス品質向上のアイデアを積極的に提案してくれやすい点もメリットといえるでしょう。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援しているクライアントへ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
主要なコールセンター代行会社の紹介
国内でも実績のある主要コールセンター代行会社の特徴と強みを簡単に紹介します。
コールセンター代行市場には、大手から中小規模まで多様な企業が参入しています。大手企業は総合力や大規模プロジェクトへの対応力が魅力であり、中小企業は特定業種に強みを持つなど、それぞれに特徴があります。
ここでは代表的なコールセンター代行会社を挙げ、特徴を概観しますが、最終的には自社のニーズと合致するかどうかを軸に選定することが重要です。
トランスコスモス
トランスコスモスは国内外に拠点をもつ大手企業で、多数のオペレータ席と豊富な導入実績が強みです。海外進出を検討中の企業や、大規模な顧客対応が必要なプロジェクト向けに適しており、AIやデジタルマーケティングの領域でも先進的な技術を活用しています。
また、チャットボットやSNS対応など、マルチチャネルでの顧客接点強化も積極的にサポートしています。人手によるサポートとデジタル技術を組み合わせることで、コスト削減と顧客満足度の向上を同時に狙える点が特徴です。
ベルシステム24
ベルシステム24は、多様な業界の顧客企業と取引実績を持つ大手コールセンター代行会社です。AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの先進技術を活用し、顧客対応の自動化や省力化を推進しています。
特に新技術の導入に積極的で、クライアントの課題に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。運用面でのサポート体制が手厚く、クレーム対応やCS向上施策など、課題解決型のプロジェクトでも実績を積んでいます。
ニッセンLINX
通販を中心とした大規模受注業務で長年の経験を持つニッセンLINXは、EC事業者に強いコールセンター代行サービスを提供しています。商品の特性や顧客心理を熟知しており、受注から配送、返品交換まで一連の流れをスムーズにサポートします。
EC業界特有のピーク時対応にも慣れているため、セール時や季節イベントなどで大量注文が発生しても、オペレーターがきめ細かく応対できる仕組みが整っています。コールセンターに加え、バックオフィス機能も任せられる柔軟性も評価されています。
ニッセンLINXのコールセンター業務支援について、詳しくはこちら
内製化と外注化の比較検討
コールセンター機能を内製化するか、外部に委託するかを検討する際のメリット・デメリットを解説します。
コールセンターを自社内で運営する方法と、専門企業へ外部委託する方法のどちらが優れているかは、一概には言えません。コストやノウハウの蓄積、人材確保など、企業の状況によって最適解は異なります。
自社で運営すれば社内ノウハウが貯まりやすい一方、人材教育や設備投資のリスクが高まる可能性があります。外注化すれば専門ノウハウを活用できるメリットがあるものの、コミュニケーションコストやセキュリティリスクを考慮しなければなりません。
内製コールセンターのメリット・デメリット
内製の場合、顧客対応から得られる知見がダイレクトに社内へ蓄積され、商品開発やサービス改善に活かしやすい点が最大のメリットです。社内でスピーディーに情報共有が行われるため、臨機応変な対応や小回りの利くサービス提供が可能となります。
しかし、設備費やオペレーターの人件費などの固定費用が高額となる傾向にあり、繁忙期などに合わせて人員を調整するのが難しい場合もあります。また、人材育成や教育カリキュラムの整備など、長期的な運用コストと手間も見逃せません。
外注コールセンターのメリット・デメリット
外注化のメリットとしては、専門的なノウハウや高い応対力を短期間で導入でき、人件費やシステム投資を抑えやすい点が挙げられます。需要変動に合わせてスケールアップ・ダウンが容易なため、変化の多い市場環境に適応しやすいという特徴もあります。
一方で、顧客の生の声が直接社内に伝わりにくいという課題や、情報伝達のミスが起きやすいリスクが存在します。定期的なモニタリングやレポート作成を義務付けるなど、コミュニケーションロスを防ぐ仕組み作りが欠かせません。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援しているクライアントへ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
コールセンター代行導入までの流れ
実際にコールセンター代行を導入する際、どのような手順を踏むのかを解説します。
コールセンター代行の導入を成功させるためには、導入目的の明確化からスタートし、複数の代行会社を比較検討したうえで、運用体制を構築していく手順が基本となります。検討プロセスを丁寧に進めることで、後々のトラブル発生を最小限に抑えることができます。
導入時にはシステム設定やオペレーター研修などが伴うため、ある程度の期間が必要です。導入後も運用状況のチェックと改善が不可欠であり、継続的なモニタリングとフィードバックにより、顧客満足度を高めていくことが可能です。
自社業務の洗い出し・目標設定
まず、どの業務を外注し、どれほどのコスト削減や品質向上を目指すのかといった目標設定から始めます。例えば、問い合わせ対応を代行することで社内のスタッフが企画や開発に専念できるようにするなど、具体的な成果をイメージすることが大切です。
洗い出した業務の優先度やボリュームを把握することで、必要とするオペレーター数や対応時間の目安が見えてきます。社内外で情報共有しながら、導入の目的を関係者全員で共有することが、スムーズなプロジェクト進行に寄与します。
複数社への資料請求・見積もり取得
自社ニーズが明確になったら、複数のコールセンター代行会社に資料請求や問い合わせを行い、詳細な見積もりを取得しましょう。同じ条件でも会社によって提示される費用や運用プランは異なるため、比較検討が欠かせません。
この段階で費用面だけでなく、対応可能な業務範囲、運営体制、セキュリティレベルなどを総合的に見極めます。担当者と具体的にコミュニケーションをとりながら、疑問点は早めに解消し、相性の良いパートナーを選定しましょう。
契約・導入後の運用フロー確立
契約が締結したら、システムへの接続やマニュアル作成などの初期設定を行い、オペレーターに対する研修を実施します。研修内容には製品知識やサービス対応の基礎だけでなく、ブランドイメージや話し方のトーンに関する研修も含まれます。
運用が開始された後は、定期的にレポートを受けたり、オペレーターの通話内容をモニタリングしたりして、品質を管理・改善していきます。企業側と代行企業が連携を密にとり、PDCAサイクルを回すことで、長期的に高い顧客満足度を維持することが可能となります。
ニッセンLINXがカスタマーサポートでご支援している株式会社ソーシャルテック様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
よくある質問と対策
コールセンター代行に関する代表的な疑問と、その対策をまとめています。
コールセンター代行は幅広い企業で導入が進んでいる一方、初めて検討する際には多くの疑問が生じるものです。ここでは、よくある質問と基本的な対処法を紹介します。
導入前の不安要素をできるだけ解消し、スムーズに業務委託を進めることが顧客満足度向上の第一歩となります。
コールセンターとコンタクトセンターの違いは?
コールセンターは電話応対が主な業務範囲ですが、コンタクトセンターはメールやチャット、SNSなども含めたマルチチャネル対応を担当する点が異なります。近年はSNSやチャットでの問い合わせも増えており、コンタクトセンターの需要が高まっています。
自社の顧客がどのチャネルを多く利用しているかを分析し、それに応じたセンター形態を選ぶことで、より効果的な顧客サービスを展開できます。
最短でどのくらいの期間から利用できる?
導入開始から実際の稼働までの期間は、依頼先のコールセンター代行会社が持つシステムや人員体制、研修スケジュールによって異なります。早いところであれば、数週間程度で立ち上げが可能な場合もあります。
ただし、マニュアル作成や教育、システム連携など準備段階が不足すると、稼働後に品質問題や運用トラブルが発生しやすくなります。短期導入を目指す場合でも、基礎固めを丁寧に行うことが成功への近道です。
委託後の品質管理や改善はどう行う?
コールセンター代行では、運用が始まった後も定期的なモニタリングとレポート分析が重要です。通話録音を確認したり、実際のオペレーションを聴き取り調査したりして、応対品質を定量・定性の両面からチェックします。
そのうえで、実際の顧客要望やフィードバックを定期的に代行先と共有し、改善策を検討・実施していくことが大切です。PDCAサイクルを回すことで、最初の契約内容・品質基準からさらに高い顧客満足度を狙うことができます。
まとめ:コールセンター代行ですぐれた顧客対応を実現しよう
コールセンター代行を導入することで、企業の顧客対応の質やコスト最適化に大きく寄与します。実態を把握し、自社に合った導入判断を追求してください。
コールセンター代行は、企業の成長に欠かせない顧客対応をプロに任せる有効な手段です。内製では手間やコストが大きい運用をスムーズに実現でき、高度なノウハウを駆使することで、顧客満足度向上や新規顧客の獲得にも寄与します。
ただし、情報漏洩リスクやノウハウ蓄積の問題など、外注ならではの課題も存在します。導入前にメリットとデメリットの両面を十分に検討し、複数の代行会社を比較しながら最適なパートナーを見つけましょう。定期的なモニタリングと改善活動を続ければ、外注コールセンターを最高の味方にすることができます。
コールセンター業務のご相談はニッセンLINXへ
ニッセンLINXでは、様々な企業のコールセンター支援を行っています。
特徴は、40年以上の運営実績と、通販業務の経験が豊富なオペレーター。
インバウンドでは受注や問い合わせ対応、アウトバウンドでは見込み客の発掘や顧客フォローを行い、営業機会を最大限に活用します。
さらに、独自のオペレーター教育プログラムにより、質の高い対応を実現。
また、コールセンターの処理業務におけるコスト削減のご提案も積極的におこなっております。
ニッセンLINXでもRPAを導入し、年間でコストが数億削減できた実績があることが背景です。
残業時間の削減や、人的エラーもなくなりミスもゼロになるといったメリットがございます。
ニッセンLINXのコールセンター代行のサービス内容詳細やRPAの導入事例は、下記の資料をご覧ください。
委託先の応答率や対応品質が悪い、、コールセンターのコストを削減したい、、業務の生産性をあげたいといった課題がありましたら、是非DLくださいませ
インバウンド、アウトバウンドを含め、ニッセンLINXのコールセンター業務支援全体については、下記ページにまとめています。
ニッセンLINXは、コールセンター業務支援を通じて、貴社の顧客満足度向上と売上拡大に貢献します。コールセンター業務のご相談はお気軽にお問い合わせください。