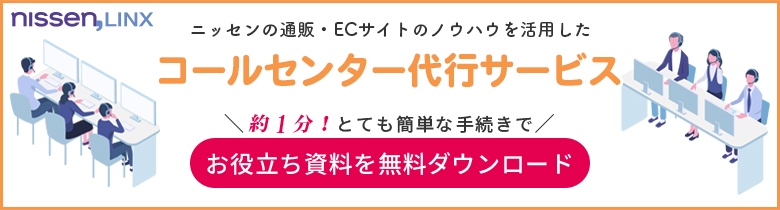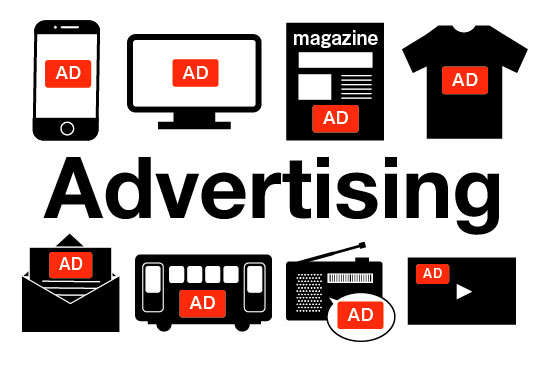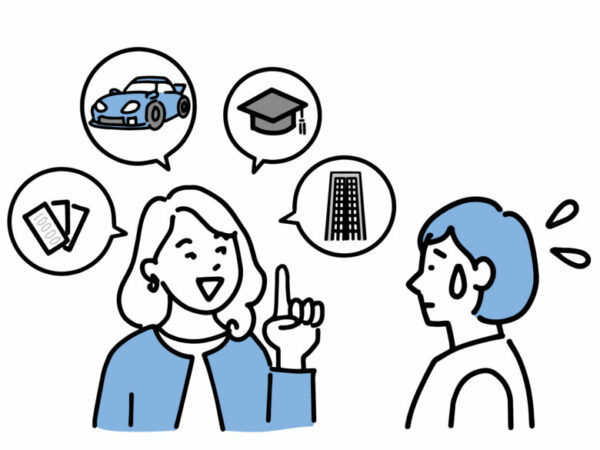企業が成長を続けるうえで、過去に取引履歴のある休眠顧客をどう再び活性化させるかは重要な課題です。いくら新規顧客を積極的に獲得しても、既存顧客が離れてしまっては継続的な売上には直結しません。本記事では、休眠顧客と離反顧客の違いをはじめ、再アクティブ化のための具体的な施策や成功事例、注意点までを解説します。
休眠顧客を適切に掘り起こすためには、まず正しく定義し、休眠に至った原因を知ることが欠かせません。そのうえで、どのような手法を用いて再度興味を引き、購入や契約を促すのかを考えていく必要があります。
すでに関係性のある顧客を再度呼び起こすアプローチは、新規開拓に比べて費用対効果が高い場合が多いです。これらを踏まえつつ、自社に合った施策を選び、休眠顧客を安定的な売上源として育成していきましょう。
40年以上のコンタクトセンター運営実績を背景にして、企業の様々な業態、サービスに合わせたコールセンターのニーズに対応いたします。
休眠顧客とは?離反顧客との違いを押さえよう
まずは休眠顧客の定義と、離反顧客との違いを明確に理解しておきましょう。
休眠顧客とは、過去に自社の商品やサービスを利用していたものの、現在は取引や接触が途絶えている顧客のことを指します。つまり、一度関係を築いたものの、しばらく利用や購入が行われていない状態です。一方で離反顧客は、積極的に他社へ乗り換えたり、解約の意志を明確に示したりするなど、再度の取引が期待しにくい顧客を指すことが多いです。
休眠顧客を再びアクティブにするためには、まず顧客がなぜ利用を止めているのかを知る必要があります。価格や品質への懸念など、原因を把握したうえで適切にアプローチできれば、再購入や再契約につながる可能性は十分あります。
新規顧客獲得の難易度が増している昨今、離反顧客よりも復帰が見込める休眠顧客をどう呼び戻すかは、企業の成長戦略において大切な鍵となります。
休眠顧客を掘り起こすメリット
休眠顧客を再アクティブ化することで得られる利点には、ビジネス成長に直結するものが多くあります。
近年、新規顧客を獲得するための広告費やマーケティング施策はますます高騰し、その成果を得るには長期的な投資が必要になっています。そこで、一度関係を築いた顧客を再度呼び戻すことは、トータルコストを抑えながら売上に直結する有効な施策になり得ます。
休眠顧客は、自社のサービスや製品を利用した経験があるため、まったく知らないブランドを初めて利用するより心理的ハードルが低い傾向があります。正しいアプローチと顧客ニーズを満たす提案を行うことで、スムーズに購買や契約につながる可能性が高いでしょう。
新規顧客開拓よりも低コスト
新規顧客の獲得には、広告費や販促費などさまざまなコストがかかります。一方、休眠顧客はすでに取引や接点があるため、その分広告やマーケティングの負担が軽減される可能性があります。
特に、メールマーケティングやDMなどの低コスト施策で再度興味を引ければ、営業リソースを多く割かなくても結果を得られることがあります。こうした点から、限られた予算でより大きなリターンを狙うことができます。
また、すでにブランド認知がある休眠顧客は、サービス内容や利用メリットの説明を省けるケースもあるため、効率的な営業活動につながるのも特徴です。
顧客生涯価値(LTV)の最大化
顧客生涯価値(LTV)は、顧客が企業の製品やサービスを利用し続けることで得られる収益の合計を指します。一度関係を築いた顧客を再度呼び戻し、継続的に利用してもらうことでLTVが増大します。
仮に一度離れてしまった顧客であっても、前向きな体験やサポートを提供すれば、再び長期的な利用へと結びつけることができます。これにより、企業としては新たな投資を少なく抑えながら収益を安定化させることができます。
長期的には、リピーターとして育成することにより口コミなどの広がりも期待でき、結果的に拡販の相乗効果を得られる可能性があります。
参考記事はこちら!➤休眠顧客とは?掘り起こしのメリットと効果的なアプローチ方法を解説
休眠顧客が生まれる4つの原因
顧客が休眠状態になる典型的な背景には、さまざまな要因が存在します。
休眠顧客を生み出す原因を細分化し、それぞれに合った対策を講じることで、休眠化を防ぐ予防策にもつながります。自社のサービスや顧客との接点を改めて見直す機会にもなりますので、しっかり押さえておきましょう。
原因ごとに再アプローチの方法が変わるため、なぜ顧客が離れてしまったのかを分析することが重要です。その結果、より適切なメッセージや施策を打ち出すことができるようになります。
商品・サービスへの不満
期待していた品質に届かなかったり、サポートが十分でなかったりすると、顧客はそのブランドから離れてしまいます。特に購入直後のサポート体制や問い合わせ対応によって顧客満足度が大きく左右されます。
品質に対する不満は、他社サービスの検討を開始するきっかけになりやすいため、迅速な対応や改善策の提示が大切です。
他社への乗り換え
競合他社が魅力的なキャンペーンや値下げを打ち出した場合、顧客が簡単に乗り換えてしまうことがあります。これは特に、価格や提供価値に大きな差があると生じやすいです。
ブランドロイヤルティを高めるには、単なる価格競争だけでなく、独自の付加価値やサービスを打ち出すことが重要です。
価格面での不安・不満
サービスや製品を使い続けるうちに、価格が高いと感じるようになったり、コストパフォーマンスに納得できなくなったりすると、利用をやめる原因となります。
価格要因の場合は、割引や特別プランなどの提案が有効な場合があります。ただし値下げだけが解決策とは限らないので、代替手段やサービス品質の向上も視野に入れる必要があります。
連絡・認知不足
顧客が自社製品を忘れてしまうほど、情報発信の頻度が極端に少ないケースもあります。こうした場合、次第に興味や関心を失い、他社製品に目移りしやすくなります。
新商品やキャンペーンの告知など、継続的かつ適切な頻度で顧客とコミュニケーションを取ることが、顧客の休眠化を防ぐうえで効果的です。
参考記事はこちら!➤休眠顧客とは?掘り起こしのメリットと効果的なアプローチ方法を解説
休眠顧客を掘り起こす前にやるべき準備
単にセールス活動を強化するだけでは十分ではありません。再アプローチには戦略的な下準備が必要です。
まずは自社における「休眠顧客」の定義を明確にすることが重要です。業種や商材ごとの購買サイクルが異なるため、何ヶ月または何年使用していない顧客を休眠とみなすかをしっかり決めます。
次に、各顧客の購買履歴や問い合わせ履歴を整理し、休眠状態に陥った背景を分析することが求められます。商材への関心度や購入金額、最後に接触したタイミングなどのデータを基に、より適切な戦略を練ることができます。
休眠顧客の定義・セグメント化
自社のビジネスモデルや商品特性に基づいて、休眠と判断する期間を設定します。あなたの業界が長い検討期間を要する場合は、より長期のスパンで見定める必要があります。
また、セグメント化によって、どの顧客層がどれくらい休眠しているかを把握できるようになります。これにより、優先度の高い顧客から順にアプローチを仕掛けることも可能です。
顧客データの整理と分析
顧客管理システムやSFA、Excelなどに散らばっている購入履歴や問い合わせ内容を整理し、統合環境を構築することが大切です。これにより、休眠に至った理由や顧客の背景を把握しやすくなります。
データ分析の結果、特定の商品ラインだけ購入がない顧客と、完全に離れてしまった顧客ではアプローチの仕方が変わります。分析で見えてきたパターンをもとに、最適なメッセージと手段を検討しましょう。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援している株式会社九州自然館様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
休眠顧客掘り起こしの主なアプローチ方法
一度離れてしまった顧客の興味を取り戻すには、複数の手段を組み合わせながら再接点を作ることが効果的です。
どのアプローチを中心に据えるかは、顧客層の属性や提供する商材、さらには自社のリソース状況によって変わります。メール配信や電話といった直接的な手段から、広告やセミナーなど間接的な手段まで、さまざまな角度から顧客にアプローチしていきましょう。
複数の施策を並行して行うときには、顧客の反応を随時チェックし、より効果の高い方法を重点的に強化する柔軟性が必要となります。
メール配信とメールマーケティング
休眠顧客を対象としたメール配信では、個々の関心や購買履歴をもとにパーソナライズを行うと効果的です。顧客の名前を入れたり、複数のアイテムの中から興味がありそうな情報だけを厳選して送るなど、きめ細やかな手法がポイントです。
定期的にメールを送ることで、連絡の断絶を防ぎ、自社の最新情報やキャンペーンを認知してもらいやすくなります。さらに、メール開封率やクリック率を分析しながら改善を続けることで、反応を高めることができます。
DM(ダイレクトメール)の活用
デジタルが主流になった時代だからこそ、紙媒体のDMを送ることで特別感を演出できます。商品サンプルや限定クーポンなどを同封することで、再度顧客の購買意欲を刺激することができます。
ただし、DMの作成や発送にはコストがかかるため、送付対象となる顧客の選定を入念に行い、費用対効果を高める工夫が必要です。
電話(テレマーケティング)
直接電話でアプローチするメリットは、リアルタイムで顧客の反応や希望を聞き出せることです。その場で疑問点や不満を解消し、改善策を提案できれば、再契約に結びつく可能性が高まります。
一方で、忙しい顧客にとってはいきなりの電話が迷惑になる場合もあるため、事前メールや適切な時間帯の選定など、相手を思いやる配慮が必要です。
MAツールとSFA/CRMの連携
マーケティングオートメーション(MA)ツールは、顧客ごとの行動履歴や関心度に応じて最適なタイミングで連絡を行うのに適しています。SFAやCRMと連携することで、部門をまたぐ顧客情報の一元管理が実現できます。
クオリフィケーション(見込み度合いの判定)を自動化することにより、有望な顧客に集中してアプローチできるため、効率的に休眠顧客を掘り起こせます。
セミナー(ウェビナー)やリアルイベント
役立つ情報を提供するセミナーやウェビナーに休眠顧客を招待することで、再びブランドとの接点を強化できます。自身の課題解決に役立つ内容であれば、顧客の関心を引きやすく、再契約や購買の可能性が高まります。
リアルイベントの場合は、実際の商品に触れたり、直接スタッフと意見交換できたりするため、距離感を縮めるのに役立ちます。イベント後のフォローアップを丁寧に行うことが大切です。
リターゲティング広告
Webサイトを訪れたものの購入や問い合わせに至らず、そのまま離脱してしまった顧客に再度アプローチを行うのがリターゲティング広告です。ブラウジング中やSNSのフィード上で繰り返し情報を表示することで、興味を取り戻す可能性があります。
ただし、広告がしつこすぎると逆効果になりかねないため、配信期間や頻度を適切に設定することが重要です。
ニッセンLINXがご支援している企業様へ、テレマーケティングのメリットやデメリット、プロモーション効果等、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
休眠顧客掘り起こしの成功事例
実際に休眠顧客の掘り起こしを成功させた企業の事例を見ると、具体的な施策の糸口が見えてきます。
あるBtoB企業では、MAツールとSFAを連携させ、休眠顧客のセグメントを自動抽出したうえで定期的なメール配信と電話フォローを行いました。その結果、初期段階で数多くの見込み顧客を再獲得でき、大幅な売上アップを達成しています。
また別の事例では、紙DMと電話を組み合わせたハイブリッド施策を実施し、従来メールを開封しない層まで効率よくアプローチしました。パーソナライズされた商品の案内やクーポンを送付することで、再度購入意欲を高めた実績があります。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援している株式会社九州自然館様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
失敗しないためのポイントと注意点
休眠顧客にアプローチする際には、逆効果にならないよう心がけるべきことがあります。
まず、相手の状況を無視した一方的な連絡は敬遠されがちです。過去の購入履歴やコミュニケーション内容に基づき、必要としている情報だけを提供するようにしましょう。そうすることで、顧客へのストレスや負担を軽減し、好印象につなげやすくなります。
また、頻度が高すぎる連絡や、配慮のない電話アプローチは顧客の信頼を損ねかねません。適切なペルソナ設定や優先度の高い顧客を見極めるなど、ターゲットを絞った手法を取り入れることが大切です。
【まとめ】休眠顧客を育成し、継続的な成果を目指そう
休眠顧客を呼び戻す取り組みは、短期的な売上向上はもちろん、企業が長期的に成長し続けるために重要な戦略です。
一度利用経験があるからこそ、適切な再アプローチで関係を修復できる可能性が高いのが休眠顧客です。新規顧客の獲得に比べ、低コストで実施できる点も大きな魅力といえます。
休眠顧客を再活性化するためには、原因分析やデータ整備から始まり、メッセージや手段を工夫することが必要です。継続的にPDCAを回すことで、より高い費用対効果を得られるでしょう。
ぜひ、本記事で紹介したアプローチや事例を参考に、御社に合った施策を見極めて実践してみてください。うまく活用すれば休眠顧客は、事業成長の強力な後押しとなるはずです。
40年以上のコンタクトセンター運営実績を背景にして、企業の様々な業態、サービスに合わせたコールセンターのニーズに対応いたします。
休眠顧客の掘り起こしはニッセンLINXへ
今回は、休眠顧客を掘り起こすためのお役立ち情報を定義からアプローチ施策について詳しく確認しました。
休眠顧客は過去に取引実績があるため、掘り起こすことができれば、新規開拓に比べて低コストかつ効率的に自社利益につながります。
休眠顧客の掘り起こしにおいては、適切なセグメントを行い、原因に応じたアプローチを取ることが必要です。
今回ご紹介したことを参考に、自社にとっての宝の山である休眠顧客の掘り起こしを、ぜひ実践してみてください。
弊社ニッセンLINXでは、カタログ販売を通じたインバウンドコールセンター業務を約50年にわたり運営してきました。また、他の企業のコールセンター業務を支援するサービスを提供しております。テレマーケティングについて課題をおもちのコールセンター管理者の方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、新規獲得支援も行っておりますので、休眠掘り起こし・新規獲得両面での貢献も可能です。
アプローチ方法などでお悩みのご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。