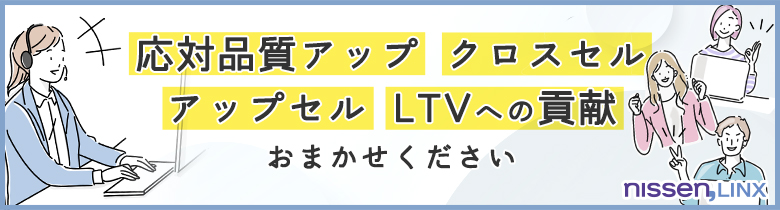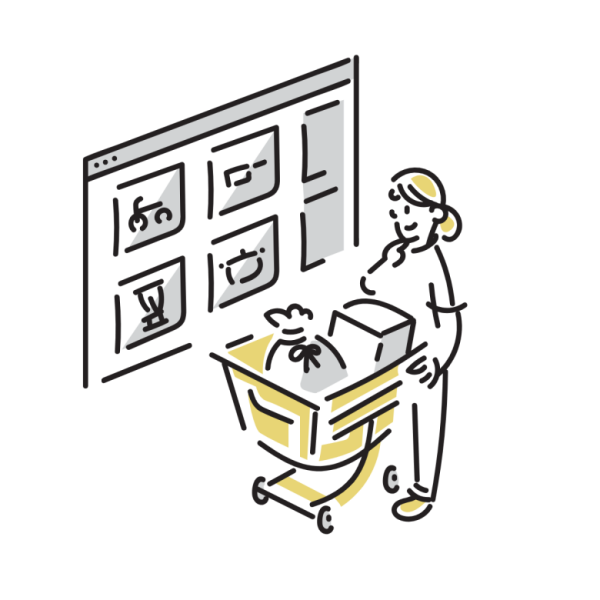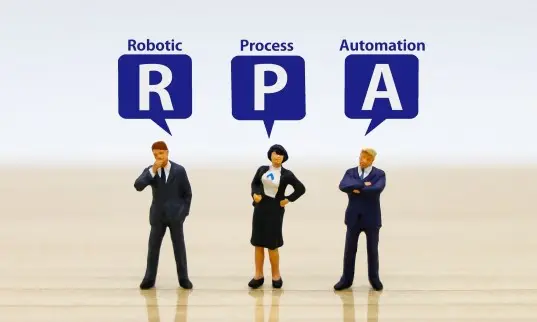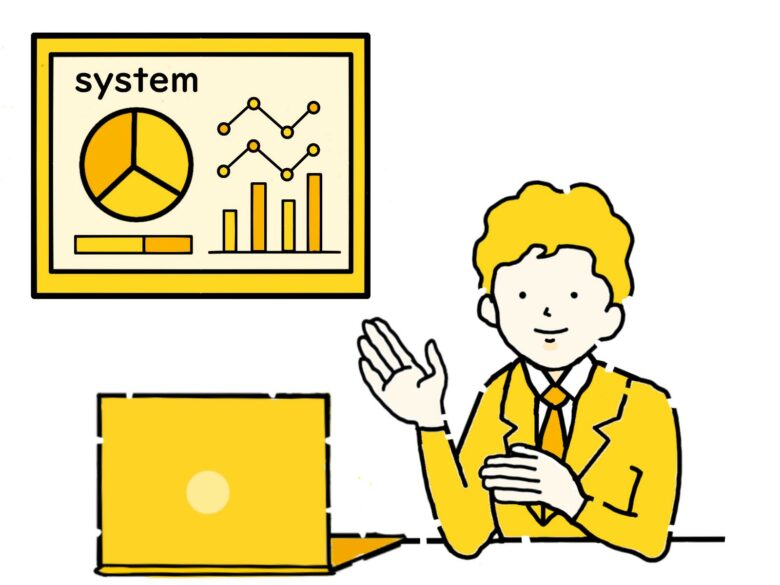売上アップに大きく寄与する施策を中心に、豊富なTipsや便利ツールも紹介していきます。さまざまな視点から対策を進めることで、ECサイト全体の顧客満足度やブランドイメージも向上していくでしょう。
また、検索結果や先行事例を踏まえ、どのようなポイントに着目すればカゴ落ちを減らせるのかを深掘りします。実践しやすい対策と長期的な運用のコツを合わせて把握することで、確かな成果につなげてください。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
カゴ落ちとは?定義と現状
まずはカゴ落ちの定義を改めて理解し、その発生状況を把握しましょう。
カゴ落ちとは、ユーザーがオンラインショップで商品をカートに入れた後、購入手続きを完了せずにサイトを離れてしまうことを指します。EC業界ではよく見られる現象であり、多くのショップ運営者が頭を悩ませる問題です。特に送料や決済方法など、購入段階で予想外の要素が発生すると離脱率が高まる傾向があります。
カゴ落ちは、多くのECサイトで売上の大きな機会損失に直結します。海外の事例などを見ても、カゴ落ち率は50%を超える場合も珍しくありません。これは運営者にとって見過ごせない数字であり、改善の余地が大いにある部分でもあります。
また、カゴ落ちを減らす取り組みは既存の顧客満足度向上にもつながります。ユーザーが使いやすいショッピング体験を得られるよう最適化を行えば、一度の購入だけでなくリピート購入へもつながりやすくなります。このように、カゴ落ち対策はECサイトの成長に不可欠な要素と言えます。
EC業界におけるカゴ落ち率の平均
一般的に、ECサイトのカゴ落ち率は60%前後と言われることが多いですが、業界や商材によっては70%を超えるケースもあります。高価格帯の商品を扱うブランドでは、検討時間が長引くことから離脱が増えやすい傾向にあります。
一方で、低価格帯の商品やデジタルコンテンツの販売サイトでは、ユーザーが比較的気軽に購入を決めるため、カゴ落ち率は低くなる傾向があります。いずれにせよ、自社の商材特性を踏まえて平均値を確認し、必要な対策を検討することが大切です。
また、近年はスマホ利用の割合が増えており、モバイルユーザー向けの最適化が進んでいないと、さらにカゴ落ち率が上昇しやすいとされています。自社サイトの閲覧デバイス別の統計を分析し、実情に合った対策を練ることが重要です。
カゴ落ちを放置するリスク:売上・顧客満足度への影響
カゴ落ちを対策せずに放置していると、ECサイト運営者にとっては大きな売上機会の損失となります。ユーザーがカートに入れた商品は購入意欲が高いと考えられますが、そこから離脱してしまうと競合他社へ流れる可能性も十分にあります。
また、ユーザーにとっては次回以降の利用ハードルが上がる恐れがあります。一度購入を取りやめた経験があるサイトでは、情報入力の煩雑さや不安を感じるなど、マイナスイメージが強く残りがちです。
これらの状況が長期的に続くと、顧客満足度やブランドイメージが低下してしまう可能性があります。カゴ落ち率の改善は単なる売上増だけではなく、リピーターの獲得や企業の信頼度向上にもつながる重要な取り組みです。
ご依頼いただいた商品を、ニッセンの休眠顧客や、他社の会員様に向けて 電話でご案内・販売し、定期顧客の獲得および送客を行います。
カゴ落ちが発生する主な原因10選
次に、ユーザーが実際にカートを放棄する原因を10項目に分けて見ていきます。
カゴ落ちの要因は多岐にわたりますが、ECサイトが抱える課題を明確にするためにも、代表的な原因を理解することが大切です。ここでは特に見逃されがちなポイントや、運営者が対処しやすい部分にフォーカスして解説していきます。
どの要因が自社サイトに深刻な影響を与えているかを把握し、優先度の高い問題から対策を進めるのが効果的です。ユーザー目線・運営者目線の両面を意識して検討しましょう。
また、原因によっては複数の対策を組み合わせて取り組む必要があります。送料と決済方法が同時にネックになっている場合には、それぞれに対策を施すことで大きく改善できるかもしれません。
原因1:送料・手数料が思ったより高い
ユーザーが商品をカートに入れる段階では、送料や手数料をあまり意識していないことが多く、注文手続きに進んだときに想定外の追加コストが発生すると大きな離脱要因になります。実際の合計金額を把握するタイミングが遅いほど、ユーザーの心理的反発が強まる可能性があります。
ECサイト上に送料や手数料を明確に表示することで、ユーザーが早い段階で合計金額を把握できるようにする工夫が必要です。また、一定額以上の購入で送料無料などの特典を用意すると、離脱を回避しやすくなります。
さらに、送料の差額を嫌うユーザーもいるため、複数の配送プランを用意して選択肢を増やすのも有効です。ユーザーが自分のニーズに合った配送方法を選べるよう配慮しましょう。
原因2:決済手段が少ない・使えない
クレジットカード決済しか使えないサイトの場合、ユーザーによっては購入を断念してしまうケースがあります。現代ではスマホ決済や電子マネー、銀行振込、代引きなど多様な決済ニーズが存在します。
特に海外のユーザーや若年層など、クレジットカード以外の手段を好む人も増えているため、複数の決済方法を導入することで離脱を予防できます。
また、決済画面でのエラーや通信障害が頻発すると、ユーザーに不信感を与えてしまいます。決済サーバーの安定性やセキュリティ対策にも十分な配慮が求められます。
原因3:会員登録やログインが必須
購入手続きの前にアカウント登録や長い個人情報入力が必須とわかると、ユーザーは面倒さを感じて離脱してしまうことがあります。初めて利用するECサイトでは、できるだけ簡素な手続きで購入できることが理想です。
ゲスト購入やSNSログインに対応することで、必要最低限の情報入力でも購入が完了する仕組みを整えるのが有効です。ユーザーへの負担を減らすことで、スムーズな決済が実現できます。
また、メールアドレス登録を促すにしても、購入プロセスにおけるタイミングやルール設定が重要です。無理に会員登録を強いるのではなく、メリットを分かりやすく提示して自然に登録を促しましょう。
原因4:入力フォーム・決済ページが複雑
ユーザーが入力しなければならない項目が多いと、一度に多くの情報を求められるためにストレスを感じてしまいます。特に、文字入力が煩雑なスマートフォンでは、小さな誤字脱字でエラーが発生すると離脱率が高まります。
ページの画面遷移や、途中でエラーになった際のリカバリーが分かりづらい場合も、途中放棄の原因になります。エラー時の挙動をわかりやすく表示し、ユーザーがスムーズに修正できる設計が大切です。
また、入力フォームを最適化するEFO(Entry Form Optimization)ツールの導入も検討すると、スムーズな入力体験を提供でき、離脱率を着実に引き下げることができます。
原因5:セキュリティ・信頼性への不安
サイトのSSL化が不十分だったり、プライバシーポリシーの記載が曖昧だったりすると、個人情報を入力する段階でユーザーが不安を抱える可能性があります。セキュリティ面の不確かさは購入意欲を大きく損ねる要因です。
実店舗との連携や、レビュー・口コミの充実度などでサイトの信頼性を高めることも有効です。顧客に「ここなら安心して買い物ができる」と思わせる工夫をサイト全体で行いましょう。
また、大手決済サービスの利用やセキュリティ認証を見える形で表示することでも、ユーザーは安心感を得られます。こうした細部の配慮がカゴ落ち率の低減につながります。
原因6:商品発送までのリードタイムが長い
配送までに数日以上かかることが明確に提示されていないと、ユーザーは後から気づいて購入をためらうケースがあります。あるいは、そもそも配送期間が他社と比べて長すぎる場合に離脱するユーザーも多いです。
特に今日の商品流通はスピードが重視される傾向が強く、迅速かつ明確な配送日程をアピールすることで競合に対する優位性を確保できます。
商品が手元に届くまでの目安を明示し、ユーザーが使いたいタイミングに間に合うかどうかを判断しやすくするのが理想です。予約販売などの場合も、発送時期を具体的に表記しましょう。
原因7:サイトの操作性・読み込み速度の問題
ページの表示が重く、商品画像や情報がなかなか読み込まれないと、ユーザーの集中力はすぐに途切れてしまいます。特にスマートフォンの回線が不安定な状況では、1秒でも待ち時間を短縮する工夫が必要です。
操作性に関しても、ボタンの配置や文字サイズなど、ユーザーが操作しやすいデザインを採用しないとストレスを感じやすくなります。ECサイトでは決済ページへの移動動線も明快であることが望ましいです。
高速表示対応やサーバー負荷の最適化は、検索エンジンの評価にもプラスに働きます。ユーザー体験だけでなくSEO面でもメリットがあるため、定期的なチェックを欠かさないようにしましょう。
原因8:クラッシュやエラーが頻発する
購入ボタンを押した際や決済ページに進む途中でエラーが発生すると、ユーザーは一気に不安を感じ、再度購入に踏み切る意欲を失いやすくなります。特にスマホユーザーがアプリやブラウザを頻繁に切り替える場合には、エラーリカバリーが複雑だとカートに戻らなくなることが多いです。
サイトのテスト環境だけでなく、本番環境での動作確認を徹底し、不具合を早期に発見・修正する体制を整えましょう。休日やセール時など、アクセスが集中するときこそ注意が必要です。
また、万が一エラーが発生した際に、カートの状態が保持されているかどうかはユーザー体験に大きく影響します。セッション管理やエラーメッセージの表示を最適化し、ユーザーが再度購入できる動線を用意しておくことが重要です。
原因9:リマインド不足で商品を忘れられる
ユーザーはカートに商品を入れた後、別のタスクに意識を奪われることも多々あります。フォローのメールやプッシュ通知がないと、そのまま商品を購入し忘れてしまうケースも少なくありません。
こうした放置を防ぐためには、カート放置者へ適切なタイミングでリマインドを送る仕組みづくりが大切です。ただし、頻繁に送りすぎるとスパム扱いされる可能性があるため、バランスを見極めましょう。
リマインドの内容には、送料や特典の再周知、購入完了までのステップを簡潔に示すなど工夫を凝らすと、ユーザーが改めて購入を検討してくれる確率が高まります。
原因10:追加費用や合計金額が事前にわからない
最終的な合計金額が購入直前になってやっと明らかになると、ユーザーは負担感を強く覚えがちです。事前に確認できれば離脱せずに済む場面で、後出しの費用が続々と発覚することでレジ落ちが増えるというパターンはよくあります。
表示方法やタイミングが不十分な場合は、ユーザーに不信感を与えかねません。追加サービスの費用やオプション料金なども含め、最初の段階で可能な限り詳細を明らかにするのが望ましいです。
あらかじめシミュレーション機能を備えておくと、たとえば商品をカートに入れたタイミングで合計金額や送料が自動計算されるため、ユーザーが安心して購入を続行しやすくなります。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
カゴ落ち率を下げるための4つの視点
様々な対策を打つ上で、重要となる4つの視点を押さえておきましょう。
カゴ落ちを改善するためには、単に一つの手段だけに頼るのではなく、複数の視点からサイト全体を最適化していくことが効果的です。どの視点も互いに影響を与え合うため、総合的な視野で改善策を考えることが成功の鍵となります。
こうした視点を考慮に入れると、単なる費用対策だけでなく、サイトデザインや顧客とのコミュニケーション手法なども見直す必要があると気づくでしょう。ユーザーにとって魅力的なショッピング体験を提供するためには、幅広い要素を総合的に強化する必要があります。
さらに、この4つの視点を踏まえた上で、日々のアクセス解析や顧客フィードバックを収集し、継続的に施策をアップデートすることも肝心です。EC業界は常に変化しているため、最新のトレンドやテクノロジーにも敏感に対応できる体制を整えましょう。
視点1:買い物フローのシンプル化
購入フローが複雑になると、多くのユーザーが途中でストレスを感じやすくなります。画面遷移を最小限に抑え、入力項目を極力削減することで、スムーズに購入を完了できるようになるでしょう。
また、フォームの自動補完機能やゲスト購入機能などを実装することで、ユーザーに余計な入力をさせない工夫が重要です。これにより、特にスマホユーザーの離脱を大きく抑えられます。
最終的にはユーザー行動分析を行い、どのステップで多くの離脱が発生しているかを把握しながら継続的に改善していくことが肝心です。
視点2:コスト・価格設定の見直し
送料や手数料はカゴ落ちの大きな原因の一つとして挙げられます。カート画面での明確な費用表示や、一定額以上で送料無料といった施策を検討することで、ユーザーへの心理的ハードルを下げる効果が期待できます。
クーポンや値引きキャンペーンを活用するのも有効です。ブランド価値を下げずに適切な割引を行うには、期間限定や特定のカテゴリ限定など、メリハリのある施策設定がポイントになります。
最終的な価格だけでなく、決済手段で発生する手数料の有無なども含めて総合的に見直し、多様なニーズに応えられる形で構築することで、ユーザーにとって使いやすい料金体系を実現しましょう。
視点3:セキュリティ対策と信頼構築
カゴ落ちを大幅に減らすためには、サイトの安全性をアピールすることが不可欠です。クレジットカード情報や個人情報の取り扱いにユーザーが不安を感じないよう、SSL証明書やセキュリティ認証を積極的に表示しましょう。
さらに、レビューや購入者の声を掲載してサイトの信頼度を高める方法も効果的です。実店舗がある場合には所在地や連絡先を明示することで、ECサイトが実在する企業であることを印象付けることができます。
また、返品・返金ポリシーを明確化し、万が一のトラブルに備えていることをユーザーに示すのも重要です。サポート体制の充実度合いが顧客満足度を左右するので、問い合わせの対応速度や窓口のわかりやすさにも注意しましょう。
視点4:顧客接点の強化
カート放置者を再度呼び戻すためには、メールやSNSなど多様なチャンネルを通じた継続的なアプローチが欠かせません。適切なタイミングでのリマインドや、購入を促すポップアップなど、顧客接点を強化する施策を検討しましょう。
チャットサポートなどを導入すれば、リアルタイムでユーザーの疑問を解消でき、離脱を防ぐことにもつながります。些細な問い合わせがきっかけで購入意欲が高まるケースも多々あります。
また、SNSでのキャンペーン情報発信や、オンライン・オフラインを組み合わせたオムニチャネル戦略を取り入れることで、多面的にユーザーにアプローチできます。カゴ落ちだけでなく、ブランドファンの育成にも役立つ視点です。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
具体的なカゴ落ち対策10選
ここからは、実践可能な具体的施策を10種類紹介します。
先に紹介したカゴ落ちの原因や基本的な視点を踏まえながら、具体的な改善アクションを見ていきましょう。ツールを使うかどうかにかかわらず、まずは手動でもすぐ着手できる対策から始めるのがおすすめです。
ポイントとしては、できるだけ短期で施策を実行し、効果検証を行いながら次の手を打つことです。すべてを一度に完璧に実装しようとすると、かえってリソースが足りずに中途半端になるリスクがあります。
ここで挙げる10個の対策は各社のECサイトの環境や規模によって優先度が変わります。自社の課題を整理して、最適な施策から順番に取り組むと良い結果につながりやすいでしょう。
~カゴ落ち対策~コールセンターの代行の参考記事はこちら➤コールセンター代行のすべて~サービス内容・費用・導入ポイントを徹底解説~
対策1:カゴ落ちメールでリマインド
カートに商品を入れたまま離脱してしまったユーザーに対して、自動でメールを送信する仕組みを導入します。一定時間や日数が経過した後、購入を促すメッセージを送ることで思い出してもらう効果が期待できます。
メールには、放置されている商品情報や写真、割引コードなどを載せると、再度購入意欲をかき立てることができます。あまり頻繁に送るとスパムと誤解される可能性があるため、送信タイミングの設定が重要です。
カゴ落ちメールは開封率やクリック率を測定しやすい施策でもあるため、定期的に内容や送信タイミングを最適化し、効果的なリマインドを届けるようにしましょう。
対策2:購入フォームのEFO(入力フォーム最適化)
入力項目を最適化し、不要な質問や重複を減らすことで、ユーザーがストレスなく入力を終えられるようにします。特にスマホユーザーに配慮し、文字入力の手間を最小限に抑えることが大切です。
EFOツールを導入することで、入力中のエラーをリアルタイムにアラート表示させたり、郵便番号入力で住所を自動補完するなどの機能を簡単に実装できます。
フォーム最適化は地味な取り組みに見えますが、その効果は大きく、離脱率を顕著に下げることが可能です。ECサイト運営においては優先度の高い施策の一つといえます。
対策3:ゲスト購入やSNSログイン対応
会員登録をせずに購入できる“ゲスト購入”機能を設けることで、初回購入時のハードルを大幅に下げられます。登録の煩雑さを嫌うユーザーを取りこぼさないためにも有効な手段です。
SNSログインを活用すると、ユーザーは新たにIDやパスワードを設定する必要がなく、簡単にアカウントを作成できる利点があります。特にスマホユーザーには大きなメリットとなるでしょう。
ただし、SNSログインには各SNSのAPI連携やセキュリティへの配慮が必要です。導入時は信頼できる連携方法を選び、万全のサポート体制を整えましょう。
対策4:多彩な決済手段の導入
ユーザーが希望する決済方法を利用できるようにすることは、カゴ落ち対策の基本と言えます。近年はQRコード決済やプリペイド型サービスなど、多様な手段が普及しているため、幅広いニーズへの対応が重要です。
ただし、導入コストや手数料のバランスを考慮し、自社のターゲット顧客が利用しそうな決済サービスを優先的に取り入れるのが賢明です。
また、決済手段だけでなく支払い時にクーポンコードを入力できるようにするなど、ユーザーがメリットを感じやすい仕組みを整えることも有効です。
対策5:送料無料やクーポン施策の活用
多くのユーザーが購入を迷う理由の一つに、送料の存在があります。一定金額以上の購入で送料無料にするなど、実質的なコストメリットを打ち出すことで離脱を防ぎやすくなります。
クーポンの発行も購買意欲を高める上で有効です。初回限定やリピート購入時などタイミングを複数用意すると、ユーザーにとって常に“お得”を感じられる機会をつくれます。
ただし、過度に割引を進めると利益率が下がり、ブランド価値を損なうリスクもあるため、提供タイミングや期間の設定には注意しましょう。
対策6:返品・交換ポリシーの明確化
購入した商品のイメージ違いや不良品など、万が一のトラブルが生じることは珍しくありません。こうした状況に迅速に対応できるかどうかが、ユーザーのサイト選択に大きく影響します。
返品・交換ポリシーをサイト上でわかりやすく提示し、手続き方法を簡単に説明しておくと、ユーザーは安心して購入に踏み切ることができます。サポート対応に対する口コミはブランドイメージにも直結します。
また、ポリシーだけでなく、お問い合わせ窓口や対応フローの分かりやすさも重要です。各連絡先やフォームの場所を明示的に案内し、ユーザーが困ったときにすぐにサポートにアクセスできるようにしましょう。
対策7:高速表示と安定したサーバー環境
読み込み速度が遅いと、ユーザーはカートまで商品を入れていても気持ちが冷めて離脱してしまうことがあります。特にキャンペーン時などアクセスが集中する場合も想定し、サーバーの増強やキャッシュ設定を適切に行いましょう。
画像の圧縮やCDNの導入など、フロントエンドの最適化も欠かせません。ページが軽快に表示されるだけで、ユーザーの購入完了率は大きく変わります。
また、サイトの安定性が低くエラーが頻発するようでは、ユーザーはそのサイト自体に不信感を持ちやすいです。定期的なメンテナンスとモニタリングを行い、安定稼働に努めましょう。
対策8:在庫状況・配送予定日の明記
商品をカートに入れた後で在庫切れだったと気づいたり、配送までの期間が不明瞭な状態だったりすると、ユーザーは購入に踏み切れません。必要な時期に届くのかどうかはとても重要な判断材料です。
在庫が少ない場合にはリアルタイムで残数を表示し、配送予定日もできる限り具体的に記載しましょう。特にギフト需要が高まる時期には、届けたい日に間に合うかどうかがカギとなります。
在庫管理システムとECサイトを連携させるなど、情報を常に最新に保つ仕組みを整えることがスムーズな購入体験の実現につながります。
対策9:アップセル・クロスセルの活用
ユーザーがカートに商品を入れた段階で、それに関連するオプションや上位モデルを提案することで、客単価を引き上げるだけでなく、購入意欲の再燃を促せる場合があります。あまり過剰な表示は逆効果ですが、ほど良い提案は有効です。
比較検討している類似商品の一覧を見やすくすると、ユーザーが迷わずにより満足度の高い商品を選ぶ手助けができます。購入時にソフトバンドルとしてまとめ買い割引を提示するのも戦略の一つです。
また、既存顧客向けにポイントや特典を加算する仕組みを作り、関連商品をセットで購入するメリットをわかりやすく示すことで、ショップ全体の売上アップにつなげることができます。
対策10:購入直前のインセンティブ
購入最終画面で、このまま買うかどうか悩んでいるユーザーに対し、クーポンやポイント還元といったインセンティブを提示すると、背中を押す効果が大きいです。
特にリピート顧客には、ログインをしている状態で特別な割引を自動適用したり、限定キャンペーンを案内するなどの施策が有効となるでしょう。
あまり多用すると通常時の購入意欲がそがれてしまうリスクもあるため、期間限定や対象商品限定などの条件を決めて活用してみるとバランスがとりやすいです。
カゴ落ち対策施策の種類と比較ポイント
ツールや施策の種類は多岐にわたるため、必要性や効果を見極めて導入することが大切です。
さまざまなカゴ落ち対策ツールやサービスが存在する一方で、自社サイトの実情に合わないものを導入しても期待した効果が得られない場合があります。まずは自社固有の課題を明確にし、ツール選定の指針を固めましょう。
比較する際は、導入コストやカスタマイズ性だけでなく、使い勝手やサポート体制も考慮する必要があります。特に日本語サポートや決済連携など、国内ECならではの要件に対応しているかを確認しましょう。
また、一度にすべての機能を使うのではなく、必要最低限の部分から実装し、効果を見ながら拡張していくアプローチも有効です。柔軟に運用できるツールを選ぶことで、長期にわたって役立つ施策を構築できます。
カゴ落ちメール配信ツール
カートに商品を入れたまま離脱したユーザーに対して、自動でメールを配信するツールです。離脱後の一定時間後に送ったり、複数シナリオを設定してフォローしたりといったきめ細かい施策が実現できます。
ユーザーごとの行動データを活用してパーソナライズした内容を送信できるツールも多く、再訪率やコンバージョン率を効率的に高められるのが特徴です。
ただし、メールが読まれる確率を上げるためにも、タイトルや文面には注意が必要です。定期的なA/Bテストを行い、メール内容を最適化していくと効果が持続しやすくなります。
EFOツール(フォーム改善)
入力フォームのUIを改善し、ストレスなくデータを入力できるように支援するツールです。フォーム入力時のエラーを防止したり、住所などを自動補完したりする機能が代表的です。
EFOツールを導入すると、ユーザーが入力作業をスムーズに終わらせられるため、途中離脱の削減につながります。特にモバイルフレンドリーな設計を求めるサイトには効果的です。
あわせて、入力項目の適正化やデザインの見直しも重要になります。ツールと運営側のデザインリソースを組み合わせて、総合的にフォーム体験を向上させましょう。
Web接客ツール・チャットボット
サイト上でユーザーの状況に応じたポップアップやチャットサポートなどを提供できるのが特徴です。疑問や不安点が即座に解消されることで、離脱を未然に防ぐ効果が期待できます。
チャットボットを活用すれば、24時間自動で一次対応が可能となり、人手が足りない場合でもある程度の顧客満足度を維持できます。高度なAIチャットボットであれば、より複雑な問い合わせにも対応可能です。
ただし、あまりに頻繁なポップアップはかえってユーザーのストレスになるため、表示タイミングや頻度を慎重に設定する必要があります。最適なバランスを見極めましょう。
マーケティングオートメーションツール
顧客の行動データや購買履歴を一元管理し、配信シナリオを自動化できるプラットフォームです。高度なリードナーチャリングが可能で、カゴ落ちユーザーに対しても随時適切なアプローチを行えます。
ECサイト以外のチャネルとも統合することで、メールやSNS、広告などマルチチャネル施策を一括で管理できるようになるのがメリットです。
導入時に必要なコストや学習コストは高めですが、大規模なECサイトや長期的な顧客ロイヤルティ構築を目指す企業にとっては非常に有用な施策となります。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
おすすめのカゴ落ち対策ツール5選
代表的なカゴ落ち対策ツールの特徴を知り、比較検討の材料にしましょう。
ここでは、カゴ落ちメールやEFO、Web接客など複数の観点で優れたサービスをピックアップしました。導入コストや機能範囲を比較し、自社に最適なソリューションを見極めてください。
ツールごとに得意分野やサポート体制が異なるため、事前に問い合わせを行ってトライアルを試してみるのもおすすめです。実際の操作感や結果を確認してから導入を決断できれば、失敗リスクを最小化できます。
ここで紹介するツール以外にも多くの選択肢がありますが、自社サイトの規模や顧客層、運営体制などを踏まえれば、自然と導入候補は絞られてくるでしょう。
1. SaleCycle:多機能カゴ落ちメール
Cartリカバリメールを中心とした多彩な機能を提供し、ユーザーごとの行動データを分析してパーソナライズしたメッセージを送ることが可能です。セグメント別に配信内容を変えられるため、効率的に離脱を防止できます。
また、オムニチャネル対応が進んでおり、メールだけでなく広告リターゲティングやSMSなどのアプローチにも活用できます。海外事例のノウハウが豊富なのも特徴の一つです。
価格帯はやや高めですが、大規模なサイト運営者であれば総合的なリカバリー施策を実行しやすいメリットがあるため、投資対効果を考慮して検討する価値があります。
2. Cuenote FC:高度なメールマーケティング
メール配信を強化したいサイト運営者には定評があるツールで、大量配信にも安定して対応できるインフラが魅力です。高い到達率を追求しており、メールが迷惑フォルダに入るリスクを抑えられます。
配信シナリオやA/Bテストの機能が充実しているので、カゴ落ちメールだけでなく通常のメルマガ施策にも応用可能です。タグ管理や細かなセグメント配信でユーザーごとに適切なアクションを取りやすくなります。
日本企業が提供しているサービスだけに、日本語でのサポートやマニュアルが充実しているのも強みです。メールマーケティングに重点を置くなら、導入を検討すると良いでしょう。
3. BOTCHAN Payment:フォーム最適化と接客
チャット形式の入力フォームを導入できるサービスで、ユーザーが自然な対話形式で情報を入力できるのが特徴です。従来のフォームよりも入力の手間が減り、離脱率を下げる効果が期待できます。
加えて、有人チャットやAIチャットボットとの併用も可能で、疑問点を即時解消しながら購入フローを進められます。UIデザインの自由度が高く、ブランディングとも合わせやすい点も評価されています。
導入の際は、既存の決済システムや顧客管理システムとの連携をチェックすることが重要です。スムーズなデータ連携が確立できれば、カート離脱者への再アプローチが一段としやすくなります。
4. フォームアシスト:EFO支援
名前や住所、電話番号などの入力補助機能が充実しており、フォームの誤入力や未入力をリアルタイムでチェックしてくれます。ユーザーはエラーを素早く修正でき、ストレスなく購入を完了しやすくなるでしょう。
デザインカスタマイズや多言語化にも対応しているため、海外向けECサイトやデザイン性を重視するブランドにも活用しやすいです。フォーム部分だけを手軽にリニューアルしたい場合にも適しています。
調整や管理画面が比較的操作しやすいと評判で、運営担当者が初めて触る場合でも導入のハードルは低めです。EFOを強化したいサイトにとって頼りになるサービスと言えます。
5. カートリカバリー:顧客ごとのリマインド最適化
ユーザー属性や行動履歴をもとに、最適なタイミングと内容でリマインドを送れるツールです。広告分野との連動も可能で、カート放置者に対してSNSやディスプレイ広告で再アプローチする仕組みを構築できます。
メールだけでなく、複数のチャネルを組み合わせてユーザーにアプローチできるため、様々なユーザー層のニーズに対応しやすい点が魅力です。
ユーザーインターフェースは比較的シンプルで、管理メニューから細かなシナリオ設定ができるので、カゴ落ち対策を一括管理したい企業には非常に便利です。
カゴ落ちアウトバウンド
メール以外の方法でユーザーに再アプローチする“アウトバウンド”の一環として、電話やSNSダイレクトメッセージを活用するケースもあります。工数がかかりますが、特に高額商品や限定商品の場合は効果の高いフォローになる場合があります。
電話によるフォローは、ユーザーとの直接的な対話を通じて不安点を解消しやすく、サイトでは得られない情報を得られるメリットもあります。ただし、プライバシーや個人情報保護の観点にも注意が必要です。
SNSでのダイレクトメッセージを送る際は、ユーザーが同意しているかどうかを確認するなど、適切なコンプライアンス対応を行いながら実施することが大切です。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
まとめ・総括
カゴ落ち率の改善はECサイトの売上や顧客満足度に直結するため、早期かつ継続的な対策が不可欠です。
本記事では、カゴ落ちの定義や原因から具体的な対策法、さらにはおすすめツールの紹介まで幅広い視点で解説しました。カゴ落ち対策を強化することで、売上機会の損失を防ぎながらリピーターを増やし、サイト全体の評価を高める効果が期待できます。
まずは、自社のカゴ落ち率や原因を把握することが最初の一歩です。そこから優先順位をつけ、取り組みやすい部分から対策を導入していくと、着実に成果が出やすくなるでしょう。
EC業界は常に変化が速いため、導入後もアクセス解析やユーザーフィードバックをもとに施策を見直すことが重要です。継続的な改善と新たな手法の取り入れによって、カゴ落ち率の低減と顧客満足度の向上を両立させていきましょう。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
かご落ちアウトバウンドのご相談はニッセンLINXへ
ニッセンLINXでは、様々な企業のコールセンター支援を行っています。
特徴は、40年以上の運営実績と、通販業務の経験が豊富なオペレーター。
かご落ちアウトバウンドから見込み客の発掘や顧客フォローを行い、営業機会を最大限に活用します。
さらに、独自のオペレーター教育プログラムにより、質の高い対応を実現。
また、コールセンターの処理業務におけるコスト削減のご提案も積極的におこなっております。
かご落ちアウトバウンドのサービス内容詳細は下記の資料をご覧ください。
入力途中でフォーム離脱したユーザーの入力情報を取得してリマインド連絡を行います。購入・申込意欲の高いユーザーにサイトへの再訪問・CVへご案内します。
インバウンド、アウトバウンドを含め、ニッセンLINXのコールセンター業務支援全体については、下記ページにまとめています。
ニッセンLINXは、コールセンター業務支援を通じて、貴社の顧客満足度向上と売上拡大に貢献します。コールセンター業務のご相談はお気軽にお問い合わせください。