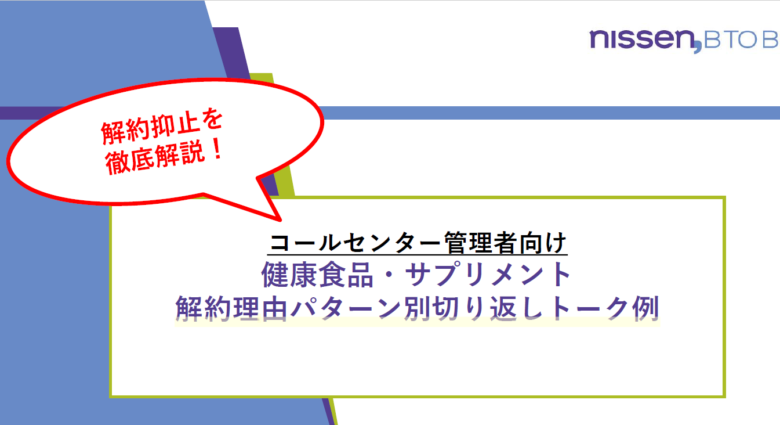健康食品マーケティングは、消費者の健康志向と法規制の理解、さらにオンライン・オフライン両面の戦略を組み合わせることで大きな成果を得られる分野です。特に、薬機法や景品表示法といった法律を正しく理解し、安全かつ効果的に商品の魅力を伝える取り組みが欠かせません。
また、ECサイトの普及によって市場は急速に拡大し、サブスクリプション型の販売モデルやターゲットに合わせたブランドストーリーの発信など、多角的なアプローチを可能にする時代になっています。
この記事では、市場の最新動向から法規制のポイント、具体的なオンライン施策とオフライン施策、実際の成功事例までを広く紹介します。これから健康食品ビジネスを始める方や、すでに展開していてさらなる成果を狙う方の一助となれば幸いです。
郵便局や温浴施設、大型スーパーなど、身近な場所のわずか2坪のスペースで、化粧品・食品・各種サービスのリアルな体験イベントを展開しています。 デジタルでは伝えきれない商品の魅力を、対面で直接お試しいただくことで、納得感のある購買や定期購入の促進につなげます。
健康食品市場の最新動向と成長要因
健康意識の高まりとともに拡大を続ける健康食品市場。その背景や主要なカテゴリー、海外動向を把握することは戦略立案の第一歩となります。
健康食品市場は、日本国内だけでなく世界的にも持続的な成長を見せています。特に、栄養補給や予防医療への関心が高まる中で、消費者は商品を選ぶ際により厳格に品質や機能を見極める傾向が強まっています。さらに、ECサイトやSNSを通じて情報収集が容易になったことで、消費者は気になるブランドや商品のレビューを入念にチェックするようになりました。
こうした背景によって、企業側からは独自の強みやストーリーを打ち出すブランディングが重要視されています。単に機能性を訴求するだけでなく、安心・安全を保証する認証取得、自社ならではの研究データやコンセプトをわかりやすく伝える工夫が求められています。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援している株式会社九州自然館様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
市場規模と消費者ニーズの変遷
健康食品市場は高齢化社会の進行や予防医療への関心を背景に、大きく規模を拡大してきました。その一方で、若い世代でも仕事や勉強に集中しながら健康を維持したいというニーズが高まっており、幅広い年齢層が興味を示しています。消費者は価格だけでなく、成分の根拠や実証データ、独自性など多面的な要素を比較検討し始めており、企業にとっては購買行動の変化を捉えたきめ細かいマーケティングが必要となっています。
健康食品のカテゴリーと機能性表示食品の位置づけ
健康食品はサプリメントや栄養ドリンク、粉末飲料、さらには特定保健用食品や機能性表示食品など多様なカテゴリーがあります。これらは商品特性や訴求ポイントが異なり、それぞれに応じたブランディングや宣伝方法が求められます。特に機能性表示食品は、企業が消費者向けに科学的根拠を示しつつ販売できるのが特徴であり、しっかりとした研究の裏付けや届出の手続きが行われた商品である点がアピールに直結します。
海外事例にみる健康食品のグローバルトレンド
欧米では免疫力をサポートするプロバイオティクスや、ストレス軽減を目的としたハーブ系サプリなどが日常生活に浸透している事例が多く見られます。アジア諸国でも漢方やハーブを取り入れた商品が人気を博し、日本企業も海外の成分や研究事例をヒントに新しい商品開発を進めています。こうしたグローバルトレンドをキャッチして、自社商品を海外市場に合わせてローカライズする動きも今後さらに重要になっていくでしょう。
健康食品マーケティングを取り巻く法規制
健康食品は法規制への理解が欠かせません。違反を避けながら適切に商品をPRするために押さえるべきポイントを確認します。
消費者の信頼を得るために、薬機法や景品表示法などの法規制を遵守して安全な広告表現を行うことが大前提となります。違法な広告を展開してしまうと企業のイメージダウンだけでなく、行政指導や罰則など大きなリスクにつながります。
一方で、正当に得た研究データや製品性能を十二分に活用できれば、他社製品との差別化を図りながら質の高い訴求を行うことが可能になります。法規制をしっかりと理解して、その枠内で最大限のアプローチを模索することが重要です。
健康食品・サプリメントでありがちな 解約理由をパターン別に切り返しトーク例として掲載しています。
薬機法(医薬品医療機器等法)と違反表現のリスク
薬機法では医薬品や医療機器と誤解される表現を禁止しており、健康食品の場合は具体的な治療効果をうたうことも認められていません。例えば「○○が治る」「病気を改善する」といった文言は違反リスクが非常に高い表現です。適切な表現としては、体の機能をサポートする旨や健康維持を助けるという範囲が中心となります。企業は開発過程や研究実績を根拠として示しつつ、誇張にならないPRを心掛ける必要があります。
景品表示法で注意すべきポイント
景品表示法では、過度な誇大広告や虚偽の表示を禁止しており、消費者に誤解を与える表現は厳格に取り締まられます。例えば、実際の効果を裏付けるデータがないまま「100%効く」「絶対に体重が落ちる」といったフレーズを使用するのは違反になり得ます。法令遵守はもちろん、顧客との長期的な信頼構築の観点からも、事実に基づき、誤解を招かない表現を徹底することが求められます。
特定保健用食品・機能性表示食品制度の最新動向
特定保健用食品(トクホ)は公的審査を通過し、特定の保健機能が認められた商品を指します。一方、機能性表示食品は企業が科学的根拠を届け出することで、比較的短時間で市場投入しやすい制度設計が特徴です。最近では、より多様な成分や働きに焦点を当てた届出が増えており、多くの企業が上手に活用することで商品価値やブランド力を高めています。
デジタル施策とECサイト運用のポイント
オンライン上での集客からリピーター獲得まで、一貫して顧客をフォローするデジタル戦略は欠かせません。具体的施策と注意点を解説します。
健康食品をECで販売する企業が増える中、デジタル施策の強化にはランディングページ(LP)の最適化や、SNS広告など多面的な集客が不可欠です。特に健康食品はリピート率が高い分、CRMなどで既存顧客との関係を維持しながら定期購入を促進する仕組みが重視されます。
また、デジタル広告を展開する際は、薬機法や景品表示法に違反しない表現を選ぶことが前提となります。正確な情報を提示しながら、わかりやすい訴求を行い、ユーザーが信頼を寄せるブランドを構築することが大切です。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援している株式会社九州自然館様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
LP制作・リスティング広告で集客力を高める
LP制作では、商品の魅力だけではなく、安全面や実際に得られる効果を具体的に伝える工夫が重要です。ユーザーが抱える悩みを解決するストーリーを盛り込み、購入ボタンを設置するタイミングや視線誘導を設計することで、転換率を向上させられます。また、リスティング広告との連動では、検索キーワードに合わせた訴求内容を細かく調整し、高い関連性を保つことがポイントです。
SNSマーケティング:Instagram・Twitter活用事例
Instagramではビジュアル重視の投稿が効果的で、商品特性を魅力的に切り取る写真や、顧客の実際の利用シーンを共有することでブランドイメージを高められます。一方Twitterでは、短文での情報発信やユーザーとのやり取りがしやすく、キャンペーン情報の拡散に向いています。近年ではSNS上の口コミから売上が爆発的に伸びた事例もあるため、企業はSNSの特性を生かしてターゲット層に合わせた広告を展開することが肝要です。
メールマガジンとCRMによるLTV最大化
メールマガジンは一度商品を購入した顧客に対して、新商品情報や季節に合った提案を行う絶好のチャネルです。定期的な接点を持つことで顧客との信頼関係を深め、長期的なリテンションを期待できます。さらに、CRMでは顧客データを分析し、購買履歴や反応率をもとに個別のアプローチを設計することで、LTV(顧客生涯価値)の向上が可能となります。
オフライン施策の活用ポイント
デジタル施策だけでなく、従来からあるオフラインでのプロモーション手法も組み合わせることで、さらに顧客への接点を拡大できます。
オフラインは一見するとコストが大きい印象がありますが、高齢者層やデジタルに馴染みのない層にも訴求できるメリットがあります。また、実際に商品を手に取ってもらえる機会が作りやすいため、安心感や信頼感を直に伝えられるのも魅力の一つです。
デジタル施策とオフライン施策を組み合わせることで、オンラインで興味を持った消費者が実店舗やイベントで実際に体験し、さらにオンラインで継続購入に繋がるといった相乗効果も期待できます。
広告主様ご自身が出演し、自社商品を120秒で紹介する短尺インフォマーシャルを、低コストかつ高品質で制作できる、Web展開にも対応したオリジナル企画です。 これまでの参入障壁を大きく下げ、テストプロモーションとしても活用可能。
新聞媒体の活用
新聞広告は中高年層を中心とした幅広い読者層へ到達しやすいのが特徴です。特に健康や生活習慣への意識が高い層が取り込まれやすく、記事体広告などを活用して詳細な商品情報を掲載することで興味関心を引き出す効果が期待できます。
テレビ広告の活用
テレビCMはマスメディアならではの圧倒的なリーチ力が魅力で、短期間で大規模な認知度向上を狙う場合に有効です。ただし制作費や放送枠などのコスト面も大きく、消費者の印象に残るストーリーや実績データをしっかり盛り込む必要があります。また、効果測定では販促や電話窓口の動向をあわせてチェックし、反響を正確に把握することが大切です。
チラシ媒体の活用
折込チラシやポスティングは特定地域に直接アプローチできるため、店舗出店エリアでの知名度アップに有効です。さらに、クーポン付きのチラシを配布すれば、興味を惹かれた人が初回購入を検討しやすくなるといった促進効果も見込めます。
テレマーケティングの活用
テレマーケティングは直接コミュニケーションを通じて顧客の疑問や不安を解消し、商品購入へとスムーズにつなげる手法の一つです。顧客の声を聞きながらフォローアップを行うことで、長期的な関係性を築き、継続購入を促専することが可能です。
催事イベントの活用
試飲や試食といったリアル体験の場を提供することで、消費者は商品の味や使い勝手をダイレクトに感じ取ることができます。実際の体感がある分、購入後の満足度も高まりやすく、口コミが自然に広がるケースが多いのも魅力です。
郵便局や温浴施設、大型スーパーなど、身近な場所のわずか2坪のスペースで、化粧品・食品・各種サービスのリアルな体験イベントを展開しています。 デジタルでは伝えきれない商品の魅力を、対面で直接お試しいただくことで、納得感のある購買や定期購入の促進につなげます。
UGC(User Generated Content)の活用術
消費者の声をマーケティングに取り入れることで、商品理解や信頼感を高めるUGC施策の考え方を学びます。
UGCは企業側が発信する情報よりも、実際に商品を使った消費者のリアルな声として高い信頼度を伴います。SNSやレビューサイトなど、多様なプラットフォームで自然に拡散されることで、商品力だけでなくブランド全体の評価にも好影響を及ぼします。
ただし、UGC活動を推進する際は、薬機法や景品表示法に抵触しないようにルールづくりやモニタリングを徹底する必要があります。正しい運用ができれば、ブランドコミュニティの形成をさらに加速させる有効な手段となるでしょう。
口コミ・レビューを活用するメリット
口コミやレビューは自然発生的に広まる特性があるため、広告費を大きくかけなくてもアイデア次第で多くの人にリーチ可能です。消費者視点の意見が集まることで、新規顧客は安心して購入に踏み切れますし、企業側は商品改善やサービス向上のヒントを得ることができます。
UGCを獲得するキャンペーン事例
ハッシュタグキャンペーンや写真投稿企画など、消費者が自発的に商品体験を投稿したくなる仕組みづくりはUGCの獲得に効果的です。例えばInstagramで商品写真に専用ハッシュタグを付けることで、検索や拡散が容易になり、多くのユーザーが参加しやすくなります。企業は応募者に対して特典や紹介枠を設けるなど、投稿者を応援する仕掛けを用意するとより成功につながりやすいでしょう。
薬機法・景表法に抵触しないUGC表現のポイント
ユーザーが自由に投稿した口コミや写真に対しても、企業側がリポストや引用する場合には注意が必要です。誤認を招く文言が含まれている投稿をそのまま再掲すると広告とみなされ、法的リスクが発生することもあります。そのため、事前にガイドラインを設けて投稿をチェックする仕組みづくりや、投稿内容に問題がある場合は修正依頼を行うなど、安全面に配慮した運用を行うことが重要です。
健康食品EC・D2Cの成功事例と戦略
健康食品ブランドがECやD2Cモデルで成功を収めるためには、定期購入の仕組みやブランドへの共感づくりが鍵となります。
ECを通じたダイレクト販売に強みを持つD2Cブランドは、製造から販売までを自社で一貫して行うことで、顧客とのコミュニケーションをより密に取ることができます。開発ストーリーを全面に押し出したブランディングや、SNSを活用した共感の輪づくりなど、既存の流通にはない顧客体験を提供できるのが特徴です。
また、D2Cを運営する上では、ターゲットに応じた強みの明確化や、メリットをしっかり伝えるUSP(独自の売り)が欠かせません。顧客ごとのデータを取得しやすいため、パーソナライズされた提案や定期利用者のフォローアップもしやすい環境が整っていると言えます。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援している株式会社九州自然館様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
定期購入モデルでリピート率を高める方法
健康食品は効果が実感しやすい長期利用が求められるケースが多いため、定期購入モデルは非常に相性が良いと言えます。例えば割引価格での提供や追加サンプルの同梱など、顧客に継続して利用してもらう工夫を設けることで、リピート率の向上につながります。会員限定の情報提供やポイント制度を活用するなど、顧客とのつながりを強化する手法も効果的です。
開発ストーリーの可視化によるブランディング効果
原料選定や研究開発の背景、開発者の想いなどをストーリーとして発信することで、顧客は商品コンセプトに共感し、より深い理解と信頼を抱きやすくなります。実際の製造現場や原産地の写真、開発過程での苦労話などを発信することは、透明性の高いブランドづくりに有効です。これにより、消費者の「どんな人が作っているのか」という疑問を解消し、ブランドへのロイヤルティを向上させます。
他社との比較による差別化と成功要因
競合他社との比較掲載は、誤解を招かない範囲で行うことが前提ですが、独自の強みを明確に伝える手段として効果的です。例えば、機能性成分の含有量や価格帯、商品コンセプトなどで差別化を図ると、消費者が「比較してみたい」と感じるきっかけになります。ただし、優位性を誇張しすぎると法令違反のリスクがあるため、実証データや客観的な事実に基づいた情報発信を心掛ける必要があります。
目的別にみる成功例と失敗例
製品の機能や訴求ポイントによってマーケティング手法は大きく異なります。各分野の成功・失敗事例を掘り下げて学びます。
健康食品には、睡眠サポートや免疫力強化、ダイエット支援、栄養補給などさまざまな目的が存在します。それぞれの商品特性に応じたプロモーションやブランドづくりが展開されており、成功事例からは多くの学びを得ることができます。
一方で、失敗事例からは表現の誤りや開発の不備など、改善すべきポイントを抽出できます。正しいデータに基づくアプローチや、消費者のニーズを的確に把握するリサーチの重要性が改めて浮き彫りとなります。
広告主様ご自身が出演し、自社商品を120秒で紹介する短尺インフォマーシャルを、低コストかつ高品質で制作できる、Web展開にも対応したオリジナル企画です。 これまでの参入障壁を大きく下げ、テストプロモーションとしても活用可能。
睡眠サポート:Yakult1000の事例
Yakult1000は睡眠の質をサポートする機能性をアピールし、大きな話題となりました。根拠となる研究データの提示や科学的裏付けによる信頼性の確保が成功要因の一つです。また、もともとヤクルトブランドが持つ認知度と、その研究体制への安心感が相乗効果を生み、定期購入を中心に売上を急拡大させることに成功した代表的なケースです。
免疫力強化:iMUSEのブランディング
iMUSEは免疫ケアを主軸とした商品展開で、コロナ禍を契機に大きく需要を伸ばしたブランドです。機能性表示食品としての根拠を明示すると同時に、手軽に取り入れられるドリンクやヨーグルトなど、多彩なラインナップを整備しました。消費者が抵抗感なく毎日の習慣に組み込みやすい形を打ち出した点が成功のカギとなっています。
ロカボ商品の訴求と失敗事例
糖質オフブームの流れでロカボ商品が急増しましたが、中には「糖質0」という誤解を招きやすい表現や、実際の成分表示が不十分でトラブルを起こしたケースも見られます。いくら話題性があっても、表示に不備があれば消費者の不信感につながり、ブランド全体の信頼を損ねる恐れがあります。実際に数社が景品表示法違反で指摘を受ける事態となり、適切な表示と透明性の確保の重要性が再認識される結果となりました。
成功を後押しする顧客体験設計とCRM施策
商品購入後の体験設計こそがリピーター獲得の要です。顧客をファン化するためのポイントや施策を見ていきます。
健康食品は、摂取を続けることで効果を実感しやすい場合が多いため、購入後のフォローアップが売上拡大に直結します。適切なタイミングでのサポート情報や新商品・キャンペーン告知など、顧客とのコミュニケーションを継続的に行う施策が重要です。
また、顧客体験の質を高めるには、単なる売買関係を越えてブランドコミュニティを育成することが効果的です。SNSやイベントを通じて情報交換の場を提供し、共通の健康目標を共有する空間を作ることで、ブランドに対する愛着や親近感を生み出すことができます。
健康食品・サプリメントでありがちな 解約理由をパターン別に切り返しトーク例として掲載しています。
顧客をファン化するコミュニケーション設計
購入前から購入後までの顧客対応をシームレスに行うことで、信頼関係を築きやすくなります。例えば、商品選定時にアドバイスを行い、購入後は摂取タイミングや組み合わせなどの利用情報を提供するなど、段階的に価値を感じてもらう設計が重要です。こうした積み重ねが顧客ロイヤルティを高め、口コミやリピート購入へとつながります。
口コミやSNS施策でブランドコミュニティを育てる
SNSやコミュニティサイトを通じて、ユーザー同士が成果や感想を共有し合う場があると、商品に対するリアルな評価と新たな発見が生まれやすくなります。企業はこれを支援する形でキャンペーンの告知や新商品発売の情報提供を行い、ユーザー間のつながりを広げる役割を果たすと効果的です。特に健康食品は個々の体質や目的によって感じ方が異なるため、多様な意見が共有されるコミュニティは購入の後押しにつながりやすいです。
リターゲティング依存からの脱却とLTV思考
デジタル広告ではリターゲティングという手法が一般的になっていますが、それだけに頼ると興味のない層にも広告が表示されるなど、費用対効果が悪化する可能性もあります。大切なのは顧客一人ひとりの累積的な購買データや行動履歴を分析し、長期的に関係を築くための施策を検討することです。顧客の満足度を高め、LTVを向上させることこそが、健康食品ビジネスの持続的な成長に直結します。
健康食品の最新トレンド予測
今後の市場を見据えた新たな取り組みや技術の動向を押さえ、今後登場するビジネスチャンスを探ります。
健康食品市場では、継続して伸びているカテゴリーがある一方で、新しい技術やライフスタイルの変化に合わせて斬新なサービスが生まれつつあります。パーソナライズ化や持続可能性への注目が高まり、これまでの一律的な商品設計から個々人に合わせたアプローチへ移行する流れがさらに強まりそうです。
また、デジタルヘルスとの連携により、健康管理の一貫として食品を取り入れるケースが増えることが予想されています。こうしたトレンドを捉えることで、新規プレイヤーにも大きなチャンスが広がるでしょう。
ニッセンLINXがカスタマーサポート、カスタマーサクセスでご支援している株式会社九州自然館様へ、弊社との取組による成果を率直に伺いました。
パーソナライズドサプリの進化と将来性
遺伝情報や日々の食事・運動データを分析し、一人ひとりに最適な栄養素を提案するパーソナライズドサプリは世界的に注目されています。既に検査キットとサプリをセットにしたサービスなども登場しており、より精緻なアルゴリズムが開発されれば、個別最適化がますます進んでいくでしょう。この領域にはまだ成長余地が大きく、新たなビジネスチャンスが潜んでいます。
サステナビリティとクリーンラベル志向の高まり
環境負荷が少なく、自然由来の原料を使用し、添加物を極力抑えるクリーンラベル志向が健康食品市場でも加速しています。サステナブルな生産体制や動物実験の削減など、エシカルな取り組みをアピールすることで、ブランドの価値向上につながるケースが増えています。消費者はこうした倫理観や企業姿勢も購買決定に含める傾向があるため、戦略的な取り組みが求められます。
デジタルヘルス領域との融合と新ビジネスチャンス
スマートウォッチや健康管理アプリと連動し、消費者のバイタルデータや行動データを解析してサプリや機能性食品の摂取を推奨するといったサービスが広がりつつあります。これにより、個別の健康課題にフィットした商品提案が可能となり、従来の「効果があるかどうか分からない」という曖昧さを減らすことが期待できます。デジタルと食品を掛け合わせた新しいビジネスモデルが今後も誕生するでしょう。
まとめ:健康食品マーケティングを成功させるために
ここまで紹介した要点を改めて整理し、今後の健康食品マーケティングを推進するために必要な考え方を提示します。
健康食品ビジネスで成果を上げるには、機能性訴求だけでなく、法規制を踏まえた適切な広告表現や販売戦略が欠かせません。また、デジタル施策とオフライン施策を融合し、顧客との多面的な接点を作り出す工夫が必要です。
さらに、購入後の体験設計や口コミを活用したコミュニティ形成といった施策も、安定的なリピート購入に繋がるカギとなります。今後はパーソナライズ化やサステナビリティ、デジタルヘルスとの連携など、多様なトレンドが登場する見込みです。こうした変化に柔軟に対応しながら、安全性と独自の価値をアピールする商品開発・販促を行うことで、健康食品マーケティングの成功を掴めるでしょう。
催事・リアルマーケティングの活用
オンラインでの販売と同時に、リアルな場でのプロモーションを活用することで、より多くの顧客に直接アプローチできる可能性が高まります。イベントや試飲会で商品を体験してもらうことにより、味や効果を直感的に理解してもらい、信頼度を大きく向上させることが可能です。これにオンラインチャネルを組み合わせることで継続購入につなげやすくなり、マーケティング全体の効果をさらに高めることができるでしょう。
郵便局や温浴施設、大型スーパーなど、身近な場所のわずか2坪のスペースで、化粧品・食品・各種サービスのリアルな体験イベントを展開しています。 デジタルでは伝えきれない商品の魅力を、対面で直接お試しいただくことで、納得感のある購買や定期購入の促進につなげます。
健康食品マーケティングのご相談はニッセンLINXへ
ニッセンLINXでは、様々な企業のマーケティングや販売促進の支援を実施しています。
長年、F3層を含む多くの女性の方々に愛用いただいてきた通販サービスの知見を元に、ニッセンLINXのカタログや商品をお客様に送付する際に、貴社のチラシを同封したり、様々なメーカーの試供品を同梱し、お客様へダイレクトにお届けすることができます。さらに、テレビ通販を活用した番組制作から、メディアバイイング、コールセンターでの受注対応など、ワンストップで支援が可能です。
企画から実施までをトータルでサポートしています。実施事例もご紹介できますので、F3層マーケティングを検討する際は、ぜひニッセンLINXへお問い合わせください。
50歳以上のアクティブシニアへのアプローチには紙、電話、WEBチャネルでニッセン会員へのリーチが可能。シニア世帯へのプロモーションをご検討なら、ご参考ください。